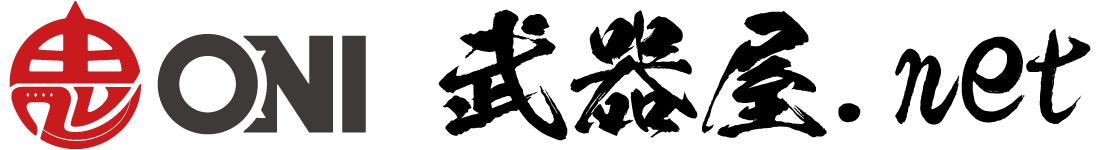Blog

【三角筋のダンベル筋トレメニュー】肩の前部・中部・後部それぞれの鍛え方
肩の筋肉・三角筋のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(前部・中部または側部・後部)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■三角筋の構造と作用●前部・中部(側部)・後部から構成される三角筋は、前部・中部(側部)・後部の三部位から構成され、全ての部位が協働して上腕を上方へ押し上げる作用を持ちます。 また、それぞれの部位の作用は以下のとおりです。 ・三角筋前部:上腕を前へ上げる・三角筋中部:上腕を横へ上げる・三角筋後部:上腕を後ろへ上げる Wikipediaによる記載三角筋の肩甲棘部は肩甲棘から、肩峰部は肩峰から、鎖骨部は鎖骨の外側部の1/3からそれぞれ起始し肩関節を覆う様に外下方へと走り上腕骨三角筋粗面に停止する。運動は肩関節を支点にして肩甲棘部が上腕を伸展・内転・外旋させ、肩峰部が上腕を外転させ、鎖骨部が上腕を屈曲・内転・内旋させる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/三角筋 ■三角筋のダンベル種目一覧(動画つき解説)ダンベルショルダープレスダンベルアップライトローダンベルサイドレイズダンベルフロントレイズダンベルリアラテラルレイズダンベルフェイスプル ■筋トレ目的別の負荷重量設定筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2b約10秒前後の短い時間に爆発的・瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a10~60秒ほどのやや長時間で瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングによりやや筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上数分・数時間の持続的・持久的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより筋肥大せずに筋密度が上がります。20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 つまり、筋肥大バルクアップ目的なら①、細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、減量引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。ただし、腹筋郡・前腕筋郡・下腿三頭筋など日常での使用頻度が高い部位は、基本的に20回以上高反復回数で鍛えます。 ■三角筋全体の代表的種目●ダンベルショルダープレスダンベルショルダープレスには座って行うシーテッドスタイルとたって行うスタンディングスタイルとがあります。 シーテッドダンベルショルダープレスは反動を使わないように、ベンチなどに座って行うバリエーション、よりストリクトに三角筋に効かせることができます。 スタンディング形式では、セット終盤で苦しくなった場合に、膝の軽い屈伸をつかってセルフ補助することが可能ですが、反動の使いすぎは効果が薄れるので注意してください。 ダンベルショルダープレスで多いのが「肩が痛くなる」ということですが、これは動作のなかで肘が体幹背面を通る軌道になってしまい、肩関節に開き負荷がかかることが主な原因です。 これを避けるためには、肘が常に体幹の前側にあるように動作する必要があります。 なお、肩に痛みや違和感を感じる場合は、ダンベルシャフトが並行になるように構えるパラレルグリップでのダンベルショルダープレスが有効です。 【本種目のやり方とフォームのポイント】 ①ダンベルを肩の上で持ち、背筋を真っ直ぐにして構える ②ダンベルを真上に押し上げていきますが、肘が身体の後ろ側に入らないように気をつける ③ダンベルを押し上げたら、同じ軌道でゆっくりと筋肉に負荷をかけながら元に戻る ■三角筋前部の代表的種目●ダンベルフロントレイズ図のように交互にダンベルを上げるバリエーションをオルタネイト式と言いますが、反動が使いにくくストリクトに効かせられるので、特に初心者の方にはおすすめです。 両方のダンベルを同時に上げるバリエーションでは、セット終盤で膝の屈伸を使ってセルフ補助を行いやすいのがメリットですが、序盤から反動を使うと効果が薄れるので注意してください。 ダンベルフロントレイズのポイントは、三角筋は体幹の大きな筋肉と連動しやすいため、反動を使わずに意識を三角筋前部に集中し、ダンベルを上げるときも下ろすときもできる限りゆっくりと動作し、しっかりと効かせることになります。 反動を使って動作を行うと、三角筋にはあまり効かず、僧帽筋ばかり効いてしまうので注意してください。 なお、反動を使えないように座って行うシーテッド式のバリエーションもあります。 【本種目のやり方とフォームのポイント】 ①背すじを真っ直ぐにし、腕を下ろした位置でダンベルをグリップして構える ②肘を伸ばしたまま、肩甲骨を寄せないように注意してダンベルを前に上げていく...
【三角筋のダンベル筋トレメニュー】肩の前部・中部・後部それぞれの鍛え方
肩の筋肉・三角筋のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(前部・中部または側部・後部)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■三角筋の構造と作用●前部・中部(側部)・後部か...

【下半身のチューブトレーニング】大腿四頭筋・ハムストリングそれぞれの鍛え方・筋トレ方法
下半身のチューブトレーニングは、女性のダイエット筋トレや男性のウエイトトレーニングの仕上げ・追い込みに最適な方法です。そのやり方を大腿四頭筋・ハムストリングス・臀筋群・内転筋群の部位別に詳しく解説します。 ■下半身の筋肉の構造と作用●太もも前面の筋肉・大腿四頭筋・大腿四頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:だいたいしとうきん英語名称:quadriceps部位詳細:大腿直筋|外側広筋|内側広筋|中間広筋起始:腸骨下前腸骨棘・寛骨臼上縁|大腿骨大転子外側面・転子間線・殿筋粗面|大腿骨粗線内側唇|大腿骨前外側面停止:膝蓋骨上縁・脛骨粗面|膝蓋骨上外側縁・頸骨粗面|膝蓋骨上内側縁・脛骨結節|膝蓋骨・頸骨粗面 大腿四頭筋は、下半身だけでなく全身でも最大の筋肉です。大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋から構成され、膝関節の伸展と股関節の屈曲補助の作用があります。 ●太もも後面の筋肉・ハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)・ハムストリングスの英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:はむすとりんぐす英語名称:hamstrings部位詳細:大腿二頭筋長頭|大腿二頭筋短頭|半膜様筋|半腱様筋起始:坐骨結節|大腿骨粗線外側唇・外側筋間中隔|坐骨結節|坐骨結節内側面停止:腓骨頭|腓骨頭|脛骨内側顆・斜膝窩靭帯|脛骨粗面内側 ハムストリングスは大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋から構成され、膝関節を屈曲させる作用があります。 ●太もも内側の筋肉・内転筋群・内転筋群の英語名称・構造・部位詳細読みかた:ないてんきんぐん英語名称:adductors muscles部位詳細:大内転筋|長内転筋|短内転筋|薄筋|恥骨筋 内転筋群は大内転筋・小内転筋・長内転筋・短内転筋から構成され、股関節を内転させる作用があります。 ●お尻の筋肉・臀筋群・臀筋群の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:でんきんぐん英語名称:gluteus muscles部位詳細:大臀筋|中臀筋|小臀筋起始:腸骨稜・腸骨翼|腸骨翼殿筋面・腸骨稜|腸骨翼停止:大腿筋膜外側部・大腿骨粗面|大腿骨大転子尖端|大腿骨大転子前面 臀筋群は、大臀筋・中臀筋・小臀筋の三層構造をしており、股関節を伸展させる作用があります。 ●ふくらはぎの筋肉・下腿三頭筋・下腿三頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:かたいさんとうきん英語名称:triceps muscle of calf部位詳細:腓腹筋外側頭|腓腹筋内側頭|ヒラメ筋起始:大腿骨外側上顆|大腿骨内側上顆|腓骨頭・脛骨後面停止:踵骨隆起|踵骨隆起|踵骨隆起 ふくらはぎの筋肉である下腿三頭筋は、腓腹筋外側頭・腓腹筋内側頭・ひらめ筋の三部位から構成されており、つま先を伸ばす作用を持ちます。 全身の筋肉のなかでも、日常での使用頻度がもっとも高い筋肉群であるため、負荷に対する耐性が高く、筋トレで鍛えにくい部位としても知られています。 ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。...
【下半身のチューブトレーニング】大腿四頭筋・ハムストリングそれぞれの鍛え方・筋トレ方法
下半身のチューブトレーニングは、女性のダイエット筋トレや男性のウエイトトレーニングの仕上げ・追い込みに最適な方法です。そのやり方を大腿四頭筋・ハムストリングス・臀筋群・内転筋群の部位別に詳しく解...

【腹筋のチューブトレーニング】腹周り・下腹・横腹・腰周りの鍛え方・筋トレ方法
トレーニングチューブ(海外ではレジスタンスバンド・エクササイズバンド)を使った腹筋のトレーニング・エクササイズ方法をまとめました。トレーニングチューブはウエイトトレーニングと違い、どのようなポジションでもセット中に負荷がかかり続けるので、とても効果が高い上に、初心者でも効かせることが簡単なのが魅力です。 また、あわせて腹筋群の拮抗筋である体幹インナーマッスル=脊柱起立筋のチューブトレーニングについてもご紹介しています。 ■まずは腹筋の構造を知る●腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋の四層構造具体的なチューブ腹筋トレーニングの解説の前に、まずは腹筋の構造を解説します。鍛える対象を知った上でトレーニングをすることは、効率的に効果を出す上で重要です。 一般的に「腹筋」と呼ばれる筋肉は、正確には四つの筋肉が折り重なった四層構造からなる筋肉群の「腹筋群」です。表層から順に、腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋となっています。 ●体幹を屈曲させる腹直筋いわゆるシックスパックの筋肉である腹直筋は、体幹を前に屈曲させる働きを持っています。 ●体幹を捻る・横に屈曲させる内外腹斜筋腹部側面に分布する外腹斜筋・内腹斜筋は体幹を捻ったり、横に屈曲させる働きを持っています。 ●腹圧を調節する腹横筋腹筋群のなかで最深層に位置する腹横筋は、腹圧を調整するコルセットのような働きを持っています。他の三つの腹筋のトレーニングのなかで二次的に鍛えることが可能です。 ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 なお、腹筋群は遅筋繊維TYPE1の比率がとても高い部位ですので、基本的には20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定でトレーニングを行います。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ 筋肉の超回復に関する記載 ■推奨されるトレーニングチューブトレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。 最大の特徴は、一般的なタイプに比べて大型のカラビナフックが付属していることで、ケーブルマシン用の各種アタッチメントなど幅広いグリップ・ハンドルが装着できることです。 また、仲介業者を介さず工場から直接仕入れをしているため、リーズナブルに提供できています。 このトレーニングチューブを見る ▼関連記事おすすめトレーニングチューブと筋肥大効果のある使い方|トレーナーが本音で解説 ■まずはアップで自重だけ腹筋運動をする●腰に負担の少ないカールアップがおすすめトレーニングチューブを使った腹筋トレーニングは、あくまでも「負荷を追加した筋トレ」ですので、いきなりチューブトレーニングからスタートするのではなく、まずはアップとして、強度の低い自重だけで行う腹筋運動を行うことをおすすめします。...
【腹筋のチューブトレーニング】腹周り・下腹・横腹・腰周りの鍛え方・筋トレ方法
トレーニングチューブ(海外ではレジスタンスバンド・エクササイズバンド)を使った腹筋のトレーニング・エクササイズ方法をまとめました。トレーニングチューブはウエイトトレーニングと違い、どのようなポジ...

【腕のチューブトレーニング】上腕二頭筋・上腕三頭筋を追い込むのに最適な鍛え方・筋トレ方法を解説
チューブトレーニングは、上腕二頭筋や上腕三頭筋の追い込み・仕上げトレーニングとして、伸びれば伸びるだけ負荷が増加する漸増負荷特性の観点から、非常に有効な筋トレ方法です。その具体的な鍛え方を、動画をまじえて解説します。 ■上腕の構造と作用●上腕二頭筋・上腕筋・上腕三頭筋・上腕は主に上腕二頭筋・上腕筋・上腕三頭筋から構成されており、各部位の特徴と作用は以下の通りです。 ○上腕二頭筋は長頭と短頭から構成されており、肘関節の屈曲(長頭・短頭)および前腕の回外(短頭)の作用があります。 ○上腕筋は肘関節基部に位置し、肘関節の屈曲作用があります。半羽状筋と呼ばれる収縮力の強い筋繊維構造をしています。 ○上腕三頭筋は長頭と短頭(内側頭・外側頭)から構成されており、肘関節の伸展(長頭・短頭)と肩関節の内転(長頭)作用があります。 ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ 筋肉の超回復に関する記載 ■推奨されるトレーニングチューブトレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。 最大の特徴は、一般的なタイプに比べて大型のカラビナフックが付属していることで、ケーブルマシン用の各種アタッチメントなど幅広いグリップ・ハンドルが装着できることです。 また、仲介業者を介さず工場から直接仕入れをしているため、リーズナブルに提供できています。 このトレーニングチューブを見る ▼関連記事おすすめトレーニングチューブと筋肥大効果のある使い方|トレーナーが本音で解説 ■上腕二頭筋のチューブトレーニング●上腕二頭筋短頭に効果的なチューブカール上腕二頭筋全体および短頭に効果的なチューブトレーニングが、チューブカールです。肘を曲げながら前腕を回外(手の平が外を向く方向に回す)すると、上腕二頭短頭が強く収縮します。 ●上腕二頭筋短頭に効果的なチューブコンセントレーションカールチューブコンセントレーションカールは、座って肘をひざの内側につき、回外回旋させる(前腕を回転させる)ことによって、上腕二頭筋短頭を完全収縮させられるチューブ筋トレです。 その名の通り、しっかりと意識を上腕二頭筋に集中(コンセントレーション)させて行ってください。 ●上腕二頭筋短頭に効果的なチューブドラッグカールこちらがチューブドラッグカールの模範的な動画です。腕を曲げ始めると同時に肘を後ろに引くように肩関節を動かし、上腕二頭筋を最大収縮させることに集中します。...
【腕のチューブトレーニング】上腕二頭筋・上腕三頭筋を追い込むのに最適な鍛え方・筋トレ方法を解説
チューブトレーニングは、上腕二頭筋や上腕三頭筋の追い込み・仕上げトレーニングとして、伸びれば伸びるだけ負荷が増加する漸増負荷特性の観点から、非常に有効な筋トレ方法です。その具体的な鍛え方を、動画...

【肩のチューブトレーニング】三角筋前部・側部・後部とローテーターカフ(回旋筋腱板)の鍛え方
肩の筋肉である三角筋とローテーターカフ(回旋筋腱板)のトレーニングチューブを使った鍛え方を、三角前部・側部・後部とローテーターカフ前面・後面の部位別に詳しく解説します。 高重量のウエイトトレーニングでは、つい反動を使ってしまい、肩の筋トレは意外と難しいものですが、チューブトレーニングだとストリクトに鍛えやすいのでおすすめです。 ■三角筋の構造と作用●前部・中部・後部に分けられ腕を前・横・後ろに上げる三角筋は前部・中部(側部)・後部に分けられ、それぞれ腕を前・横・後ろに上げる作用があり、三部位が共働して腕を上に上げる作用もします。 ■ローテーターカフ(回旋筋腱板)の構造と作用●棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋から構成され肩関節を回内・回外・内旋・外旋・内転・外転ローテーターカフは肩甲骨周辺のインナーマッスルで、肩甲骨後面の棘上筋・棘下筋・小円筋、肩甲骨前面の肩甲下筋から構成され、肩関節を回内・回外・内旋・外旋・内転・外転させるといった複雑な作用をつかさどっています。 このため、投げる、打つといった動作が多いスポーツ競技において、競技能力向上に重要なだけでなく、肩の損傷予防にも鍛えておく重要性の高い筋肉群です。 ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ 筋肉の超回復に関する記載 ■推奨されるトレーニングチューブトレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。 最大の特徴は、一般的なタイプに比べて大型のカラビナフックが付属していることで、ケーブルマシン用の各種アタッチメントなど幅広いグリップ・ハンドルが装着できることです。 また、仲介業者を介さず工場から直接仕入れをしているため、リーズナブルに提供できています。 このトレーニングチューブを見る ▼関連記事おすすめトレーニングチューブと筋肥大効果のある使い方|トレーナーが本音で解説 ■三角筋全体のチューブトレーニング●チューブショルダープレス三角筋全体に効果的で、肩のチューブトレーニングの基本とも言えるのがチューブショルダープレスです。腕を上げる時に三角筋前部と側部、負荷に耐えながら腕を下ろす時に後部に効果がありますので、どちらの動作もゆっくりコントロールして行ってください。 ●チューブアップライトロー三角筋トレーニングは、大胸筋や背筋群に負荷が逃げやすくやや難易度が高いのですが、チューブアップライトローイングは比較的動作が簡単で効かせやすい種目です。肘を前に出すと三角筋前部に、後ろに引くと三角筋後部に効かせやすくなります。 ■三角筋前部のチューブトレーニング●チューブフロントレイズ三角筋前部を集中的に鍛えられるのが、チューブフロントレイズです。初心者の方には、腕を交互に上げるオルタネイト式のやり方が動作がしやすくおすすめです。 ■三角筋中部のチューブトレーニング●チューブサイドレイズ三角筋中部を集中的に鍛えられるのが、チューブサイドレイズです。腕を上げる時だけでなく、下げる時もチューブの負荷に耐えながら動作すると、さらに効果的です。...
【肩のチューブトレーニング】三角筋前部・側部・後部とローテーターカフ(回旋筋腱板)の鍛え方
肩の筋肉である三角筋とローテーターカフ(回旋筋腱板)のトレーニングチューブを使った鍛え方を、三角前部・側部・後部とローテーターカフ前面・後面の部位別に詳しく解説します。 高重量のウエイトトレーニ...

【背中のチューブトレーニング】広背筋・僧帽筋のゴムバンドでの鍛え方
背筋のチューブトレーニングは、懸垂などの自重トレーニングやダンベルローイングなどのダンベル筋トレの後の仕上げや追い込みトレーニングに最適な鍛え方です。 また、トレーニングチューブは伸びれば伸びるほど負荷が増加する漸増負荷という特性があるのもメリットです。そのトレーニング種目を動画とともに解説します。 ■背筋の構造と作用●広背筋・僧帽筋・長背筋群から構成され引く動きをする背筋には主に表層筋の広背筋と僧帽筋、その深層に位置する脊柱沿いのインナーマッスルである長背筋群から構成されています。その作用は以下の通りです。 ○広背筋:上や前から腕を引く作用があります。 ○僧帽筋:下から腕を引き肩甲骨を引き寄せる作用があります。 ○体幹を伸展させ姿勢を維持する作用があります。 なお、長背筋群は広背筋や僧帽筋のトレーニングのなかで自然に鍛えられますので、本記事では広背筋と僧帽筋を鍛えるチューブトレーニング種目を解説していきます。 ●広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:こうはいきん英語名称:latissimus dorsi muscle部位詳細:上部|下部●僧帽筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:そうぼうきん英語名称:trapezius muscle部位詳細:上部|中部|下部●長背筋群・脊柱起立筋の英語名称・構造・部位詳細読みかた:せきちゅうきりつきん英語名称:erector spinae muscle部位詳細:腸肋筋|最長筋|棘筋長背筋群=脊柱起立筋+多裂筋+回旋筋など ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ 筋肉の超回復に関する記載 ■推奨されるトレーニングチューブトレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。...
【背中のチューブトレーニング】広背筋・僧帽筋のゴムバンドでの鍛え方
背筋のチューブトレーニングは、懸垂などの自重トレーニングやダンベルローイングなどのダンベル筋トレの後の仕上げや追い込みトレーニングに最適な鍛え方です。 また、トレーニングチューブは伸びれば伸びる...