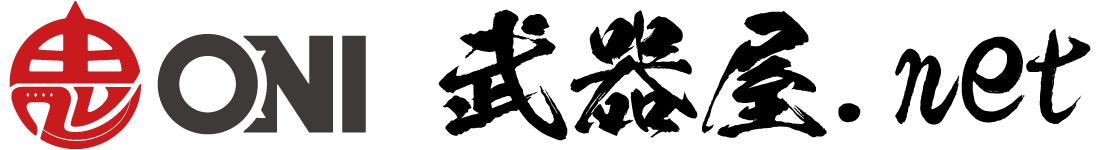背筋のチューブトレーニングは、懸垂などの自重トレーニングやダンベルローイングなどのダンベル筋トレの後の仕上げや追い込みトレーニングに最適な鍛え方です。
また、トレーニングチューブは伸びれば伸びるほど負荷が増加する漸増負荷という特性があるのもメリットです。そのトレーニング種目を動画とともに解説します。
■背筋の構造と作用
●広背筋・僧帽筋・長背筋群から構成され引く動きをする

背筋には主に表層筋の広背筋と僧帽筋、その深層に位置する脊柱沿いのインナーマッスルである長背筋群から構成されています。その作用は以下の通りです。
○広背筋:上や前から腕を引く作用があります。
○僧帽筋:下から腕を引き肩甲骨を引き寄せる作用があります。
○体幹を伸展させ姿勢を維持する作用があります。
なお、長背筋群は広背筋や僧帽筋のトレーニングのなかで自然に鍛えられますので、本記事では広背筋と僧帽筋を鍛えるチューブトレーニング種目を解説していきます。
●広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:こうはいきん
英語名称:latissimus dorsi muscle
部位詳細:上部|下部
●僧帽筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:そうぼうきん
英語名称:trapezius muscle
部位詳細:上部|中部|下部
●長背筋群・脊柱起立筋の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:せきちゅうきりつきん
英語名称:erector spinae muscle
部位詳細:腸肋筋|最長筋|棘筋
長背筋群=脊柱起立筋+多裂筋+回旋筋など
■チューブトレーニングの効果を上げる方法

チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。
①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせる
チューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。
②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える
各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。
③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させる
トレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。
④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする

筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。
①速筋繊維TYPE2b
およそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。
②速筋繊維TYPE2a
30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。
③遅筋繊維TYPE1
60秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。
つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。
チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。
■超回復とは

筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。
この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。
よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。
●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報
”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)”
▼厚生労働省公式ページ
■推奨されるトレーニングチューブ

トレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。
最大の特徴は、一般的なタイプに比べて大型のカラビナフックが付属していることで、ケーブルマシン用の各種アタッチメントなど幅広いグリップ・ハンドルが装着できることです。
また、仲介業者を介さず工場から直接仕入れをしているため、リーズナブルに提供できています。
▼関連記事
おすすめトレーニングチューブと筋肥大効果のある使い方|トレーナーが本音で解説
■チューブトレーニングの前におすすめの筋トレ
チューブトレーニングは、冒頭でも解説したとおり自重トレーニングやダンベルトレーニングなどの仕上げ・追い込みに最適なトレーニング方法です。逆に、それだけでは十分な負荷がありませんので(特に男性の場合)、チューブトレーニングの前に以下のようなトレーニングで背筋をある程度疲労させておく必要があります。
●順手懸垂(プルアップ)
背筋トレーニングの王道とも言え、非常に効果の高いトレーニングが順手懸垂です。チンニングと呼ばれることもありますが、厳密にはチンニングは逆手懸垂のことで、正しくはプルアップと言います。

懸垂と言えば、どうしても顎をバーから上に出すことに固執してしまいますが、純粋にトレーニングとして考えた場合は上図のように「胸をバーにつけにいく」というのが大切です。また、あわせて「肩甲骨を寄せる」「やや上を見る」というのも大切なポイントです。
●ダンベルローイング
ダンベルで背筋を鍛える代表的な種目がダンベルローイングです。ダンベルローイングにはいくつかバリエーションがありますが、なかでもワンハンドダンベルローイングは可動域が広く、特に広背筋に効果的ですのでおすすめです。

その動作のポイントは、背中を反らせて肩甲骨を寄せながらダンベルを引き上げることのほかに、胸を張りやや上を見るようなフォームで行うことです。
■背筋全体のチューブトレーニング
●背筋全体に効果的なチューブデッドリフト
こちらの動画は、ヨーロピアンスタイルと呼ばれる、幅を狭く置いた両足の外側をグリップして行うチューブデッドリフトのものです。
デッドリフト系種目は背筋群に高い効果がある反面、間違ったフォームで行うと腰や膝に負担がかかるので注意が必要です。
デッドリフト系種目の基本的なフォームのポイントは以下のようになります。
・胸を張る
・背筋を伸ばす
・やや斜め後ろにしゃがむ
・目線を上にして立つ
・最後に肩甲骨を寄せる
・膝がつま先より前に出ないようにする
デッドリフト系種目でもっとも避けなくてはいけないのが「背中が丸まる」ことです。胸を張り、目線を上に向けて動作を行うことで、背中が丸くなるのを防ぐことができます。
●下半身も同時に鍛えるチューブワイドデッドリフト
こちらの動画のように、広く開いた両足の内側をグリップして行うスタイルを、チューブワイドデッドまたはチューブスモウデッドリフトと呼びます。
通常のヨーロピアンスタイルのデッドリフトに比べ、下半身の使用率が高く、背筋群と下半身を同時に鍛えたい場合におすすめです。
胸を張りやや尻を突きだして前傾姿勢で構え、両手を結ぶ線の中心がヘソの真下にくるような軌道で上半身を起こしていきます。
下を見ると背中が丸くなり、背筋に対する効果が半減しますので、必ず上を見ながら動作してください。
また、膝関節保護のため、膝をつま先より前に出さないようにすることも大切です。
■広背筋のチューブトレーニング
●広背筋側部に効果的なチューブラットプル
広背筋のなかでも側部に効果の高いチューブトレーニングが、チューブラットプルです。高い場所にチューブトレーニングを取り付けることで上から腕を引く軌道を作ります。動作のポイントは、順手懸垂とほぼ同じで、胸を張りながら肩甲骨を寄せることです。
なお、高い場所にトレーニングチューブを取り付けることができない場合は、こちらの動画のように、自分自身が前かがみになり「上から腕を引く」軌道をつくることで対応が可能です。
●広背筋中央部に効果的なチューブベントオーバーロー
広背筋のなかでも中央部に効果的なチューブトレーニングがチューブベントオーバーローです。筋トレの基本スタイルであるニーベントスタイルで行います。

なお、ニーベントスタイルは①胸を張る②背中を反らせる③お尻を突く出す④上を見る⑤膝をつま先より前に出さない、というのがポイントで、多くの筋トレで必要な基本フォームですので、この機会に習得しておくとよいでしょう。
●広い可動域で広背筋側部に効果的なチューブワンハンドローイング
こちらがチューブワンハンドローイングの模範的な動画です。
本種目の最大のメリットをいかし、できるだけ大きな動きで広背筋を最大伸展・最大収縮させてください。
また、腕を引きながら肩甲骨を寄せていき、最後に肩甲骨を寄せきって広背筋を完全収縮させることがポイントです。
■僧帽筋のチューブトレーニング
●僧帽筋に効果的なチューブローイング
背筋群のなかでも、僧帽筋に対して効果の高いチューブトレーニングがチューブローイングです。上体を倒しすぎると上手く効きませんので、上体は90度程度に維持し、胸を張って肩甲骨を寄せながら腕を引いてください。
●僧帽筋に集中的に効くチューブショルダーシュラッグ
チューブショルダーシュラッグは、僧帽筋に集中的な効果があります。肩甲骨を動かすことだけに集中し、他の部位を使わないようにすることが大切なポイントです。
●最後の追い込みに最適なチューブリバースフライ
自重トレーニング・ダンベル筋トレ→チューブトレーニングとトレーニングを進めてきた最後に、総仕上げとして最適な種目がチューブリバースフライです。ゆっくりとした動作で確実に筋肉を追い込み、オールアウトしてください。
■脊柱起立筋のチューブトレーニング
●脊柱起立筋に効果的なチューブグッドモーニング
チューブグッドモーニングは、脊柱起立筋を中心として背面のインナーマッスルである長背筋群に効果的なトレーニング種目で、こちらが模範的な動画です。
腰を痛めないために、折り返しポイントで反動を使わないこと、上半身を床と平行より低くは倒さないことが大切です。
また、本種目はインナーマッスルのトレーニングですので、身体を下ろす時も上げる時もゆっくりとした動きで動作を行い、アウターマッスルを使わないようにすることが大切です。
●脊柱起立筋を高負荷で鍛えるチューブバックエクステンション
こちらがチューブバックエクステンションの模範的な動画です。ポイントは脊柱起立筋に負荷を集中できるよう、アウターマッスルである僧帽筋や広背筋を使わないようにすることです。
このためには肩関節を動かさず、また、身体を起こす時も下ろす時もゆっくりとインナーマッスルに届くように動作を行うことが大切です。
また、腰を痛めないためにも、必要以上に上半身を反らせたり、折り返し点で反動を使わないようにしてください。
■最強のハイブリッド筋肥大メソッド
①自重トレーニング+トレーニングチューブ
チューブトレーニングは、それ単体では筋肥大効果はあまり強くありませんが、自重トレーニングに負荷としてチューブの漸増負荷を加えることで、大きな筋肥大効果が期待できます。
・バックエクステンション+トレーニングチューブ
こちらの動画が、バックエクステンションにトレーニングチューブの負荷を追加したやり方です。
ローマンベンチを使用して行うハイパーバックエクステンションは、バックエクステンション系種目のなかでも最高強度のトレーニング方法で、そこにトレーニングチューブの漸増負荷が加わりますので、かなりの高負荷筋肥大トレーニングになります。
なお、バックエクステンションの動作ポイントは以下の通りです。
①長背筋群の筋収縮と首の連動性を考慮して「下を見ない」ことが大切です。下を見ながら動作を行っても長背筋群は最大収縮せず、適切の効果を得ることができません。前を見て動作を行ってください。
②反動を使って反復を行うと、腰椎に強い負荷がかかり腰痛の原因になります。反動は使わず、ゆっくりとして動作を心がけてください。
②ダンベル筋トレ+トレーニングチューブ
トレーニングチューブの漸増負荷をダンベル筋トレと組み合わせることで、とても強い筋肥大効果が得られることが知られており、ボディービル選手などにも使用者は少なくありません。
・ダンベルローイング+トレーニングチューブ
こちらの動画が、ダンベルローイングにトレーニングチューブの負荷を追加したやり方です。
ワンハンドダンベルローイングはベンチなどに片手をついて行うダンベルローイングで、自身の姿勢を100%支える必要がないので、高重量のダンベルを引き上げることに集中できるのが大きなメリットです。胸を張り、やや顎を上げて行うのは基本と同じです。
また、ダンベルローイングのバリエーションのなかで、もっとも広背筋の可動範囲が広くなりますので、広背筋をターゲットにする場合におすすめの種目です。
なお、動画のように前方にトレーニングチューブをセットすることで「下方へ腕を引く軌道」となり、通常のダンベルローイングでは効かせにくい広背筋側部に負荷をかけられますので、自宅での逆三角形トレーニングにも最適です。