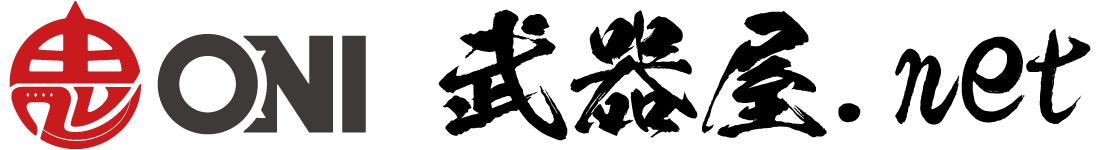Blog

【アイスクリームのカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
アイスクリームのカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。アイスクリームとはどんな食べ物?アイスクリーム(英: ice cream)は、牛乳などを原料にして、冷やしながら空気を含むように攪拌してクリーム状とし、これを凍らせた菓子である。そのうち、柔らかいものは「ソフトクリーム」と呼ばれる。 引用:Wikipedia「アイスクリーム」 アイスクリーム類の種類日本国内においてアイスクリーム類は、その乳脂肪分の含有率によって、多い順にアイスクリーム・アイスミルク・ラクトアイス・氷菓の四種類に規格が分けられています。国によっては「アイスクリーム」製品の規格を規定する場合がある。例えば日本では乳固形分及び乳脂肪分が最も高いアイスクリームと、アイスミルク、ラクトアイスの3種類を合わせて広義に「アイスクリーム類」と称す。乳成分をほとんど含まず、クリーム状でない氷菓もアイスクリームに括られることも多い。 引用:Wikipedia「アイスクリーム」 アイスクリームのカロリー・栄養素アイスクリーム100gあたりのカロリー・栄養素は以下のとおりです。 エネルギー:180kcalタンパク質:3.9g (15.6kcal)脂質:8g (72kcal)炭水化物:23.2g (92.8kcal) ※数値は「食品成分データベース(文部科学省)」を参照しています。 食事の三大栄養素について食事の三大栄養素(エネルギー産生栄養素)とは、タンパク質(protein)・糖質(carbohydrate)・脂質(fat)の三種類です。そして、その三種類の栄養素の頭文字をとって、栄養素バランスのことをPFCバランスと呼びます。この三種類の栄養素の特徴とグラムあたりのカロリーは以下の通りです。 ○タンパク質(4kcal/g)タンパク質は筋肉を構成する物質で、筋トレで鍛えた筋肉を大きくするための材料となります。 ○糖質(4kcal/g)糖質は活動のためのエネルギー源になるだけでなく、タンパク質を筋肉として合成する時の筋肉合成カロリーとして働きます。 ○脂質(9kcal/g)脂質も糖質と同様のエネルギー源としての働きを持ちますが、グラムあたりの熱量が高く、貯蔵エネルギーとして効率的なので、余剰カロリーは体脂肪として貯えられます。 厚生労働省による三大栄養素に関する記載エネルギー産生栄養素(えねるぎーさんせいえいようそ) 食物中に含まれる身体に必須の成分のうち、たんぱく質・脂質・炭水化物の総称。 人間の身体になくてはならない栄養素のうち、エネルギー(カロリー)源となる「たんぱく質・脂質・炭水化物」を『エネルギー産生栄養素』と呼んでいます。以前は、三大栄養素とも言われていました。 引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-013.html アイスクリームと筋力トレーニングアイスクリームは若干のタンパク質を含むカロリー食品で、筋肥大トレーニングにおいてはトレーニング前のカロリー補給やトレーニング後の食事のカロリー追加に有効です。ダイエットトレーニングにおいては、カロリーオーバーになりがちですので、ラクトアイスや氷菓など他のアイスクリーム類を選ぶとよいでしょう。アイスクリームの具体的レシピ例【バナナ豆腐アイスクリーム】筋トレやダイエットにおすすめのヘルシースイーツ トレーニングに有効なタンパク質食材筋力トレーニング後の食材として欠かせないのが高タンパク質・低カロリーな肉類・魚介類です。そして、常にトレーニングに有効な食事を摂取するためには、日によって品質にばらつきのないよう、あらかじめ品質を確認した食材を冷凍ストックしておくといった工夫が有効的です。 ▼具体的なタンパク質食材例筋力トレーニングに有効な肉類・魚介類 食事・栄養に関する記事筋力トレーニングと食事・栄養に関する情報については、下記の記事をご参照ください。筋力トレーニングと食事筋力トレーニングの栄養学筋力トレーニングと栄養補助食品筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
【アイスクリームのカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
アイスクリームのカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。アイスクリームとはどんな食べ...

膝関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺筋のトレーニング方法
膝関節を構成する骨格と筋肉について解説するとともに、膝関節周辺の筋肉のトレーニング方法についても解説します。膝関節を構成する3つの骨膝関節は大腿骨・脛骨・膝蓋骨の3つの骨から構成されています。膝関節(しつかんせつ)は、膝にある関節。膝関節は大腿骨と脛骨と膝蓋骨から成る関節であり、機能的には蝶番関節に近く、構造的には顆状関節に分類される。膝関節の関節半月は線維軟骨で構成される。 引用:Wikipedia「膝関節」 膝関節を構成する筋肉膝関節は、太ももの筋肉である大腿四頭筋(大腿直筋・外側広筋・中間広筋・内側広筋)およびふくらはぎ周辺の筋肉である腓腹筋・膝窩筋・足底筋から構成されています。また、このほかに膝関節の周辺にはハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)・縫工筋・下腿三頭筋(腓腹筋・ひらめ筋)・前脛骨筋などがあります。膝関節周辺の筋肉のトレーニング方法下半身の筋力トレーニング縫工筋の作用と鍛え方前脛骨筋の作用と鍛え方下腿三頭筋の作用と鍛え方骨格の名称と付随する筋肉人間の骨格と付随する筋肉筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
膝関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺筋のトレーニング方法
膝関節を構成する骨格と筋肉について解説するとともに、膝関節周辺の筋肉のトレーニング方法についても解説します。膝関節を構成する3つの骨膝関節は大腿骨・脛骨・膝蓋骨の3つの骨から構成されています。膝...

肘関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺インナーマッスルのトレーニング法
肘関節構成する骨格と筋肉について解説するとともに、肘関節周辺インナーマッスルのトレーニング方法についても解説します。肘関節の3つの骨と関節肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成されており、それぞれ腕橈関節(上腕骨と橈骨)、腕尺関節(上腕骨と尺骨)、上橈尺関節(橈骨と尺骨)と呼ばれる3つの関節からできている複関節です。肘関節(ちゅうかんせつ)は、肘にある関節。肘関節は上腕骨と橈骨、尺骨から成る関節であり複関節に分類される。蝶番関節としても分類される。 引用:Wikipedia「肘関節」 肘関節を構成する筋肉肘関節は、前腕屈筋群に属する円回内筋・橈側手根屈筋・尺側手根伸筋・長掌筋・浅指屈筋、前腕伸筋群に属する長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・尺側手根伸筋・回外筋、および上腕伸筋群に属する肘筋から構成されています。肘関節周辺の主な深層筋の鍛え方肘筋の作用と鍛え方腕橈骨筋の作用と鍛え方長橈側手根伸筋の作用と鍛え方橈側手根屈筋の作用と鍛え方円回内筋の作用と鍛え方骨格の名称と付随する筋肉人間の骨格と付随する筋肉筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
肘関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺インナーマッスルのトレーニング法
肘関節構成する骨格と筋肉について解説するとともに、肘関節周辺インナーマッスルのトレーニング方法についても解説します。肘関節の3つの骨と関節肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成されており、...

股関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺インナーマッスルのトレーニング法
股関節を構成する骨格と筋肉について解説するとともに、股関節周辺インナーマッスルのトレーニング方法についても解説します。股関節を構成する骨格股関節は骨盤骨の窪みである寛骨臼に大腿骨の先端である大腿骨頭がはまるようにして構成されている球関節です。また、股関節周辺には恥骨・脊椎骨(腰椎・仙堆・尾堆)が位置しています。股関節(こかんせつ)は寛骨臼と大腿骨頭よりなる球関節(関節部分が球形(股関節の他に肩関節))であり、荷重関節(体重などがかかる関節(他に膝関節など))である。大腿骨頭は半球を上回る球形で、寛骨臼は深く大腿骨頭を収納するように形成され、大腿骨頭が容易に脱臼できない仕組みになっている。 引用:Wikipedia「股関節」 股関節を構成する筋肉股関節を構成している主たる筋肉には、大腿直筋(大腿四頭筋)・腸腰筋群・内転筋群・臀筋群・大腿方形筋・縫工筋・梨状筋などがあります。股関節周辺の筋肉のトレーニング方法腸腰筋群の作用と鍛え方内転筋群の作用と鍛え方臀筋群の作用と鍛え方大腿方形筋の作用と鍛え方縫工筋の作用と鍛え方骨格の名称と付随する筋肉人間の骨格と付随する筋肉筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
股関節の構造|構成する骨格と筋肉|周辺インナーマッスルのトレーニング法
股関節を構成する骨格と筋肉について解説するとともに、股関節周辺インナーマッスルのトレーニング方法についても解説します。股関節を構成する骨格股関節は骨盤骨の窪みである寛骨臼に大腿骨の先端である大腿...

肩関節の構造|構成する骨格と深層筋|肩甲骨周辺のトレーニング
広義の肩関節5種類とそれを構成する骨格および主たる周辺深層筋について解説します。あわせて、これら肩関節・肩甲骨周辺のインナーマッスルの筋力トレーニングのやり方についても解説します。肩関節とは狭義の肩関節(第一肩関節・第二肩関節)一般的に肩関節と言えば、肩甲骨と上腕骨の接合部分である第一肩関節(肩甲上腕関節)のことを指し、これに加えて肩峰~烏口突起間にある烏口肩峰靭帯と上腕骨の間隙である第二肩関節を含める場合もあります。肩関節(けんかんせつ)は、肩にある関節。一般的には肩甲上腕関節(第一肩関節)の事を指し(肩甲骨と上腕骨をつなぐ間の部分で、肩甲骨の関節窩と上腕骨頭で形成された関節部分)、これを狭義の肩関節という。 引用:Wikipedia「肩関節」 広義の肩関節(肩甲胸郭関節・肩鎖関節・胸鎖関節)このほかに、広義の肩関節に含められるものには、胸骨と鎖骨の接合部分である胸鎖関節、肩甲骨と鎖骨の接合部分である肩鎖関節、胸郭と肩甲骨の間隙である肩甲胸郭関節があります。広義の肩関節は、肩甲骨、上腕骨、鎖骨、胸骨、胸郭に関連する5つの関節(文献によっては、肩甲上腕関節・肩鎖関節・胸鎖関節の3つの場合もある)で構成されており、肩複合体と呼ばれることもある。 引用:Wikipedia「肩関節」 肩関節周辺の主たる深層筋(インナーマッスル)回旋筋腱板(ローテーターカフ)ローテーターカフは肩甲骨に張りつくように位置している棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の四つの筋肉から構成されています。このうち、棘上筋・棘下筋・小円筋は肩甲骨の背面側に、肩甲下筋は肩甲骨の胸側に位置して拮抗関係にあります。棘上筋による肩関節の動き(参照画像)回旋筋腱板(ローテーターカフ)の鍛え方回旋筋腱板は肩関節周辺インナーマッスルとして、腕の動作に非常に重要で、投げる、打つなどのスポーツ競技ではそのトレーニングが最重要とされています。肩と肘を固定して行うインターナルローテーションやエクスターナルローテーションなどの種目で鍛えます。回旋筋腱板(かいせんきんけんばん Rotator cuff)は肩甲骨の前面と後面からおこる4つの筋、すなわち肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の腱のことをいう。回旋腱板または、英語のカタカナ表記でローテーター・カフともいう。 上腕骨頭をかかえ込んで肩関節を安定させるはたらきがある。そのため腕を使う運動には全て密接に関係しており、このローテーターカフをうまく連動させて使えるかどうかによって運動の効率が全く変わってしまう。 引用:Wikipedia「回旋筋腱板」 回旋筋腱板はトレーニングチューブやダンベルを使ったインターナルローテーション(肩甲下筋)・エクスターナルローテーション(棘上筋・棘下筋・小円筋)と呼ばれる種目で鍛えることができます。▼回旋筋腱板のトレーニング https://bukiya.net/blog/rotator-cuff/ 鎖骨下筋鎖骨下筋は第一肋骨と鎖骨下面にまたがる胸部筋肉の一種で、鎖骨を前下方に引き下げる作用を持っています。また、上腕の運動時に胸骨と鎖骨との間の関節である胸鎖関節を安定させる働きを持っています。鎖骨下筋(さこつかきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうちの一つ。肋骨(第1)を起始とし、上外方に集まりながら、鎖骨の下面に停止する。 鎖骨を前下方に引き下げる作用がある。 引用:Wikipedia「鎖骨下筋」 鎖骨下筋の鍛え方鎖骨下筋だけをターゲットに鍛えられるトレーニング種目はありませんが、鎖骨を前下方に引き下げる動作をともなうトレーニング種目のなかで表層筋と同時に刺激を加えることは可能です。鎖骨下筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。 ▼動画つき解説 ディップス チューブチェストフライ チューブプルオーバー ダンベルフライ ダンベルプルオーバー マシンチェストフライ ケーブルフライ バーベルプルオーバー sfphes.orgより 烏口腕筋烏口腕筋は上腕二頭筋短頭よりさらに上腕内側上方に位置する筋肉で、上腕の屈曲と内転の作用があります。上腕屈曲時には上腕二頭筋や上腕筋と協同して作用します。烏口腕筋(うこうわんきん)は人間の上肢の筋肉。名の通り起始部が烏口突起から起こり、内下方に向かっては上腕骨の内側前面中部に停止する。支配神経は腕神経叢の外側神経束の枝である筋皮神経である。 作用としては上腕の屈曲と内転を行う。屈曲時には上腕筋、上腕二頭筋などと共に協調して働く。 引用:Wikipedia「烏口腕筋」 烏口腕筋の鍛え方烏口腕筋だけをターゲットに鍛えられるトレーニング種目はありませんが、上腕屈曲動作をともなうフロントレイズ系やアームカール系のトレーニング種目のなかで表層筋と同時に刺激を加えることは可能です。烏口腕筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。 ▼動画つき解説...
肩関節の構造|構成する骨格と深層筋|肩甲骨周辺のトレーニング
広義の肩関節5種類とそれを構成する骨格および主たる周辺深層筋について解説します。あわせて、これら肩関節・肩甲骨周辺のインナーマッスルの筋力トレーニングのやり方についても解説します。肩関節とは狭義...

胸郭の構造|構成する骨格と筋肉|胸囲を増す拡張トレーニングの方法
胸郭を構成する骨格と筋肉、呼吸の仕組みについて解説するとともに、胸囲を増し大胸筋の土台を拡げるためのトレーニング方法についても解説します。胸郭を構成する骨格と筋肉胸郭を構成する骨格胸郭は胸骨・肋骨(第1~12)・胸椎(第1~12)および肋軟骨から籠状に構成されています。胸郭を構成する筋肉胸郭は胸壁筋群(外肋間筋・内肋間筋・肋下筋・長肋骨挙筋・短肋骨挙筋・胸横筋)および横隔膜から構成されており、胸式呼吸においては胸壁筋群が、腹式呼吸においては横隔膜が強く関与します。ヒトの胸郭(英:thorax、独:Brustkorb、羅:thorax, pectus)は頚部と腹部の間にあり、心肺など生体重要臓器を容する体部で、円錐台形の籠状の構造になっており、弾力性に富む。胸郭後方には支柱となる12の脊椎がある。この脊椎を起点として12対の肋骨が前下方へ向かい、側方から再び上へ向かい、肋軟骨を介して胸骨と繋がり、肋骨籠 rib cage を構成する。この骨組に肋間筋その他の胸部諸筋、筋膜、横隔膜が付着して胸郭となり、その内壁を肋膜が覆って胸腔 thoracic cavity を形成する。 引用:Wikipedia「ヒトの胸郭」 胸郭拡張トレーニングとはボディビルディング競技やボディメイクトレーニングでは、大胸筋の土台となる胸郭を拡張するための胸郭トレーニングが実施されます。この胸郭トレーニングは、息が上がるスクワットなどの直後に、胸に息をためたままプルオーバー系種目を行いますので、呼吸を利用したトレーニング方法とも言えるでしょう。特に10代後半から20代前半の若い年齢層においては、10cm前後も胸囲が増したという事例も知られています。胸郭拡張トレーニングの実施方法胸郭拡張トレーニングはバーベルやダンベルを用いた低負荷高レップス(20レップス前後)の直後に、息が上がった状態でインターバルをおかずにバーベルプルオーバーやダンベルプルオーバーを実施し、胸郭に対してストレッチングをかけるという手法で実施します。これら、胸郭拡張を目的としたスクワットやプルオーバーは、ブリージングスクワット、ブリージングプルオーバーとも呼ばれ、呼吸方法と組み合わせた形で実施されます。 ブリージングスクワットのやり方 ブリージングプルオーバーのやり方 sfhes.orgより プルオーバー種目と胸郭の動作この動画は、ダンベルプルオーバー時に大胸筋・広背筋だけでなく胸郭を構成する骨格・軟骨がどのように動作するかを再現した3DCG動画です。プルオーバー種目実施時のイメージ作りにご活用ください。骨格の名称と付随する筋肉人間の骨格と付随する筋肉筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
胸郭の構造|構成する骨格と筋肉|胸囲を増す拡張トレーニングの方法
胸郭を構成する骨格と筋肉、呼吸の仕組みについて解説するとともに、胸囲を増し大胸筋の土台を拡げるためのトレーニング方法についても解説します。胸郭を構成する骨格と筋肉胸郭を構成する骨格胸郭は胸骨・肋...