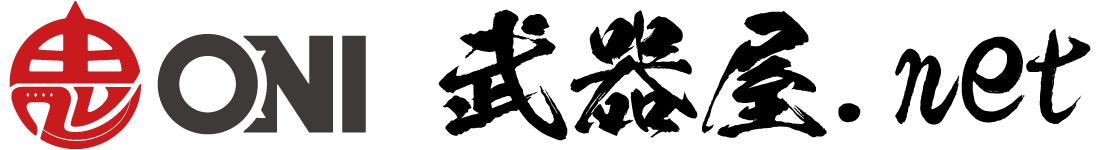Blog

【女性の自重ダイエット筋トレメニュー】家での一週間プログラム例
自宅ですぐに取り組める、女性のためのダイエット自重トレーニングメニューを解説するとともに、一週間の具体的なプログラムを例示解説します。 なお、本記事では下記の公的サイトの情報に基づき記載をしております。 ▼運動プログラム作成の原理原則 運動プログラム作成のための原理原則 -安全で効果的な運動を行うために ■ダイエット筋トレの有効性●運動していない時でもカロリー消費が発生し続ける筋トレを行うと筋肉痛になり、それを回復させるために数日間は基礎代謝カロリーの消費量が向上します。 運動している時にしかカロリー消費のおきない有酸素運動などより、はるかにダイエットに適した運動です。 ●自重トレーニングダイエットのメリット自重トレーニングの最大のメリットは、器具がなくてもいつでもどこでもできる、という手軽さです。そして、思い立ったらすぐに始められるので「痩せよう!」という気持ちが熱いうちにダイエットをスタートできます。 これまで、筋トレの経験のない女性も多いと思いますが、まずは、何も入らないのでやってみましょう。 ■ダイエット筋トレの反復回数●20回を1セットの目安に遅筋をターゲットにする筋トレ、という言葉を聞くと、どうしても女性はムキムキになってしまうのでは? と不安になりがちですが、筋肥大を起こす筋肉は速筋と呼ばれる瞬発運動に使われる筋肉で、トレーニングでは15回以下の強い負荷で鍛えます。 ダイエット筋トレでは、速筋を刺激することを避け、筋肥大しない遅筋(持久筋)を20回以上の低負荷高反復回数で刺激していきますので、ムキムキになることはありません。 ■ダイエット筋トレの呼吸法●力を入れる時に口から吐き戻ってから鼻から吸う筋トレのような運動は、無酸素運動と呼ばれる筋細胞内のグリコーゲンを直接燃焼させますが、ダイエット筋トレのように多い反復回数で行う場合には、有酸素運動の要素もくわわります。 ダイエット筋トレ時に同時発生する有酸素運動を、より効果的にするためには腹式呼吸が有効で、このためには「鼻から吸って口から吐く」呼吸を行うだけで、自然と腹式呼吸になります。 なお、筋肉は息を吐く時に収縮する(力が入る)特性があります。ダイエット筋トレにおいては、力を入れながら口から息を吐き、元のポジションに戻ってから鼻から息を吸う、というのが最も効率的な呼吸方法です。 ■ダイエット筋トレの頻度●週四回全身を部位分けしてローテーションするのがベスト筋トレをすると筋肉痛になり、それが回復する時の代謝エネルギー上昇を利用して痩せるのが、ダイエット筋トレの基本メソッドですが、1日に全身をトレーニングしてしまうと、筋肉痛がおさまるまで数日間は筋トレを行えません。 これでは、かなり非効率です。 そこで、全身の筋肉を動きの連動性によってグループ分けし、一週間をかけてローテーションでトレーニングをしていくのが効率的です。 ダイエット筋トレに相性のよい分割方法は、全身を四つのグループに分け、それぞれ週に1回ずつ、週に4回のトレーニング頻度で筋トレを行っていく方法です。 ■全身の部位のグループわけそれでは、具体的に全身の筋肉を部位分けしていきましょう。 ①上半身の押す筋肉 ・大胸筋:胸の筋肉・三角筋:肩の筋肉・上腕三頭筋:二の腕後側の筋肉 ②上半身の引く筋肉 ・僧帽筋:首の後ろの筋肉・広背筋:背中の筋肉・上腕二頭筋:二の腕前側の筋肉 ③体幹の筋肉 ・腹筋群:お腹の筋肉・長背筋:背骨沿いの筋肉 ④下半身の筋肉 ・大腿四頭筋:太もも前側の筋肉・ハムストリングス:太もも後側の筋肉・臀筋群:お尻の筋肉・下腿三頭筋:ふくらはぎの筋肉 なお、さらに詳しい筋肉の名称と作用は以下の筋肉名称図鑑をご参照ください。 ▼筋肉名称完全図鑑...
【女性の自重ダイエット筋トレメニュー】家での一週間プログラム例
自宅ですぐに取り組める、女性のためのダイエット自重トレーニングメニューを解説するとともに、一週間の具体的なプログラムを例示解説します。 なお、本記事では下記の公的サイトの情報に基づき記載をしてお...

【バーベル筋トレメニュー】BIG3と筋肉部位別の各種目を詳細に解説
筋トレBIG3と呼ばれるウエイトトレーニングの基本中の基本種目=ベンチプレス・デッドリフト・スクワットに関して解説します。あわせて、各派生種目および全身の筋肉部位別の代表的なバーベル筋トレについてもご紹介します。 ※筆者が運営するトレーニングジムで実際に実践・指導している経験をもとに執筆しています。 ※筋トレと食事に関するネット情報はさまざまですが、当サイトでは下記の公的機関の情報に基づいて記載しています。 ▼運動プログラム作成の原理原則 運動プログラム作成のための原理原則-安全で効果的な運動を行うために なお、本格的なバーベルトレーニングの実施に際しては、いわゆるフィットネスジムなどではなく、フリーウエイトトレーニング専門のジムで実施することが器材の充実度やトレーナーの専門性の観点などから推奨されます。 フリーウエイト専門トレーニングジムの一例 ■まずは全身の筋肉をグループ分け●上半身の押す筋肉・引く筋肉・体幹の筋肉・下半身の筋肉トレーニングを始める前に、ぜひ知っておきたいのが全身の筋肉の名称・作用と共働する(一緒に動く)筋肉のグループ分けです。鍛える対象をしっかりと把握しておくことは、筋トレの効果を出すためにとても大切なことです。 全身の筋肉は、一般的に上半身の押す筋肉・引く筋肉・体幹の筋肉・下半身の筋肉に分けられますが、そのグループを構成する主な筋肉の名称と作用を以下にまとめました。 ●上半身の押す筋肉グループ上半身の押す動作をする筋肉のグループには、胸の筋肉・大胸筋、肩の筋肉・三角筋、腕の筋肉・上腕三頭筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○大胸筋:上部・下部・外側・内側に分けられ、腕を前方に押し出すしたり腕を前方で閉じる作用があります。 ○三角筋:前部・中部・後部に分けられ、腕を前や横に上げる作用があります。 ○上腕三頭筋:長頭・内側頭・外側頭から構成され、肘を伸ばす作用があります。 ●上半身の引く筋肉グループ上半身の引く動作をする筋肉のグループには、背中の筋肉・僧帽筋と広背筋、腕の筋肉・上腕二頭筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○僧帽筋:下から腕を引いたり肩甲骨を引き寄せる作用があります。 ○広背筋:中央部と側部に分けられ、それぞれ前や上から腕を引く作用があります。 ○上腕二頭筋:長頭と短頭に分けられ、肘を曲げる作用があります。 ●体幹の筋肉グループ体幹の筋肉のグループには、体幹前面の筋肉・腹筋群と体幹背面の筋肉・長背筋群、股関節周辺の筋肉群・腸腰筋群や臀筋群があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○腹筋群:腹直筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹横筋の四層構造をしており、体幹を屈曲・回旋させる作用があります。 ○長背筋群:脊柱沿いの筋肉群で最長筋・多裂筋・脊柱起立筋などから構成され、体幹を伸展・姿勢維持の作用があります。 ○腸腰筋群:大腰筋・腸骨筋などから構成される股関節と大腿部をつなぐ体幹前面の筋肉群で、脚を前に持ち上げる作用があります。 ○臀筋群:大臀筋・中臀筋・小臀筋の三層構造をした股関節と大腿部をつなぐ体幹後面の筋肉群で、脚を後ろに持ち上げる作用があります。 ●下半身の筋肉グループ下半身の筋肉のグループには、太もも前面の筋肉・大腿四頭筋、太もも背面の筋肉群・ハムストリングス、ふくらはぎの筋肉・下腿三頭筋筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○大腿四頭筋:大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋に分けられ、膝関節を伸展させる作用があります。 ○ハムストリングス:大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋から構成され、膝関節を屈曲させる作用があります。 ○下腿三頭筋:ふくらはぎの筋肉で足首を伸ばす作用があります。 なお、さらに詳しい筋肉の名称と作用は以下の筋肉名称図鑑をご参照ください。 ▼筋肉名称図鑑【筋肉の名前と作用の完全図鑑】筋トレ部位の名称と共働筋・拮抗筋|その鍛え方 ■筋トレBIG3とは●ベンチプレス・デッドリフト・スクワットの3種目筋トレBig3と呼ばれる種目がありますが、それは、ベンチプレス・デッドリフト・スクワットの3種目のことです。この3つの筋トレを行えば、ほぼ全身がくまなく鍛えられることから、このように呼ばれています。また、パワーリフティング競技の公式3種目です。 ■ベンチプレスと派生種目ベンチプレスは主に大胸筋・三角筋・上腕三頭筋に効果があるバーベル筋トレメニューで、上半身の押す筋肉を発達させる上で基本となる種目です。...
【バーベル筋トレメニュー】BIG3と筋肉部位別の各種目を詳細に解説
筋トレBIG3と呼ばれるウエイトトレーニングの基本中の基本種目=ベンチプレス・デッドリフト・スクワットに関して解説します。あわせて、各派生種目および全身の筋肉部位別の代表的なバーベル筋トレについ...

【初心者のジムマシン筋トレメニュー】筋肉部位別の種目と筋肉をつける一週間のプログラム例
トレーニングジムに入会したものの、初心者の方はどんなマシンでどこをどう鍛えればいいのかわからないかと思います。また、トレーナーが有料だったり、無料でも忙しそうで声をかけづらいことも少なくありません。 そこで、ジムに入会したての初心者の方が、全身をしっかり鍛えられるように、筋肉部位別のスタンダードなマシン筋トレメニューをご紹介するとともに、具体的な一週間のプログラムの組み方を例示します。 なお、初心者の方は、週に二回が一般的なトレーニング頻度ですので、週に2回のもっとも効率的な筋トレメニュープログラムを前提に進めていきます。 ※筋トレと食事に関するネット情報はさまざまですが、当サイトでは下記の公的機関の情報に基づいて記載しています。 ▼運動プログラム作成の原理原則 運動プログラム作成のための原理原則 -安全で効果的な運動を行うために ■まずは全身の筋肉をグループ分け●上半身の押す筋肉・引く筋肉・体幹の筋肉・下半身の筋肉トレーニングを始める前に、ぜひ知っておきたいのが全身の筋肉の名称・作用と共働する(一緒に動く)筋肉のグループ分けです。鍛える対象をしっかりと把握しておくことは、筋トレの効果を出すためにとても大切なことです。 全身の筋肉は、一般的に上半身の押す筋肉・引く筋肉・体幹の筋肉・下半身の筋肉に分けられますが、そのグループを構成する主な筋肉の名称と作用を以下にまとめました。 ●上半身の押す筋肉グループ上半身の押す動作をする筋肉のグループには、胸の筋肉・大胸筋、肩の筋肉・三角筋、腕の筋肉・上腕三頭筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○大胸筋:上部・下部・外側・内側に分けられ、腕を前方に押し出すしたり腕を前方で閉じる作用があります。 ○三角筋:前部・中部・後部に分けられ、腕を前や横に上げる作用があります。 ○上腕三頭筋:長頭・内側頭・外側頭から構成され、肘を伸ばす作用があります。 ●上半身の引く筋肉グループ上半身の引く動作をする筋肉のグループには、背中の筋肉・僧帽筋と広背筋、腕の筋肉・上腕二頭筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○僧帽筋:下から腕を引いたり肩甲骨を引き寄せる作用があります。 ○広背筋:中央部と側部に分けられ、それぞれ前や上から腕を引く作用があります。 ○上腕二頭筋:長頭と短頭に分けられ、肘を曲げる作用があります。 ●体幹の筋肉グループ体幹の筋肉のグループには、体幹前面の筋肉・腹筋群と体幹背面の筋肉・長背筋群、股関節周辺の筋肉群・腸腰筋群や臀筋群があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○腹筋群:腹直筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹横筋の四層構造をしており、体幹を屈曲・回旋させる作用があります。 ○長背筋群:脊柱沿いの筋肉群で最長筋・多裂筋・脊柱起立筋などから構成され、体幹を伸展・姿勢維持の作用があります。 ○腸腰筋群:大腰筋・腸骨筋などから構成される股関節と大腿部をつなぐ体幹前面の筋肉群で、脚を前に持ち上げる作用があります。 ○臀筋群:大臀筋・中臀筋・小臀筋の三層構造をした股関節と大腿部をつなぐ体幹後面の筋肉群で、脚を後ろに持ち上げる作用があります。 ●下半身の筋肉グループ下半身の筋肉のグループには、太もも前面の筋肉・大腿四頭筋、太もも背面の筋肉群・ハムストリングス、ふくらはぎの筋肉・下腿三頭筋筋があり、それぞれの作用は以下の通りです。 ○大腿四頭筋:大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋に分けられ、膝関節を伸展させる作用があります。 ○ハムストリングス:大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋から構成され、膝関節を屈曲させる作用があります。 ○下腿三頭筋:ふくらはぎの筋肉で足首を伸ばす作用があります。 なお、さらに詳しい筋肉の名称と作用は以下の筋肉名称図鑑をご参照ください。 ▼筋肉名称図鑑 【筋肉の名前と作用の完全図鑑】筋トレ部位の名称と共働筋・拮抗筋|その鍛え方 ■筋肉グループを二つに組み合わせる●超回復と筋肉量を考慮した最適な組み合わせ方次に、週二回のトレーニングを想定して、四つの筋肉グループを一日目に鍛える筋肉グループ群と二日目に鍛える筋肉グループ群に組み合わせます。...
【初心者のジムマシン筋トレメニュー】筋肉部位別の種目と筋肉をつける一週間のプログラム例
トレーニングジムに入会したものの、初心者の方はどんなマシンでどこをどう鍛えればいいのかわからないかと思います。また、トレーナーが有料だったり、無料でも忙しそうで声をかけづらいことも少なくありませ...

【自重トレーニングメニュー】限界突破の最強筋肥大筋トレの一週間の組み方
大胸筋・背筋・腕などの基本的な自重トレーニングメニューを解説するとともに、限界を突破して筋肥大するための負荷のかけ方や適切な回数設定の方法もご紹介します。あわせて、一週間の効果的なプログラムの組み方も例示します。 本記事では下記の公的サイトの情報に基づき記載をしております。 ▼運動プログラム作成の原理原則運動プログラム作成のための原理原則-安全で効果的な運動を行うために ■自重トレーニングで筋肥大するか?●答はイエス・ただし工夫が必要筆者(アームレスラー)がハンマーカールの持ち方を解説するために撮影した自分自身の写真です。ボディービルダーの方々に比べると、決して筋肉が太いとは言えないかもしれませんが、「筋肉を太くしたい」と考える一般的な男性からすると筋肥大した身体と言えるとは思います。 実際、トレーニングジムを運営している筆者ですが、基本的にバーベルやダンベルを使ったトレーニングはほとんど行いません。 アームレスリングは対人コンタクト競技なので、フレキシブルに使える筋肉の鍛え方をしたいと考え、ほとんどのトレーニングは腕立て伏せ・ディップス・懸垂など「原始的な」自重トレーニングで行っています。 よく、「自重トレーニングでは筋肥大しない」という声もありますが、そんなことはないと考えています。実際、100kgですので懸垂をすれば100kgのラットプルダウンに等しいですし、ディップスをすれば上腕三頭筋にかかる負荷は100kgのベンチプレスとあまりかわりません。 もちろん、体重が軽い方は、その体重負荷だけでは負荷不足になるかもしれませんが、ウエイトをぶら下げたり担いだりして懸垂や腕立て伏せをすれば、十分に筋肥大に必要な負荷を筋肉に与えることができます。 こちらは、筆者のジムで練習とトレーニングをしていたアームレスリングU21全日本チャンピオンですが、このように鎖を巻きつけ、二段懸垂を行うことで、筋肥大に十分な負荷を得られています。 また、筋肥大を促すために、あえてスロースピードで動作を行うなど、自重トレーニングも工夫次第で十分に筋肥大は可能です。 ■筋肥大のための負荷・回数設定●10回前後で限界がくるように調整する筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2b約10秒前後の短い時間に爆発的・瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a10~60秒ほどのやや長時間で瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングによりやや筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上数分・数時間の持続的・持久的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより筋肥大せずに引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ・筋肥大目的なら①の10回前後の反復回数で限界がくるように、重りを身につけるか動作自体をゆっくり行うことで、負荷を調整することが可能です。 なお、腹筋に関しては、その筋繊維の構成として遅筋繊維がとても多いので、20回の反復回数で鍛えていくのが一般的です。 ●自重トレーニングは毎日していいか?よくある誤解に「自重トレーニングはウエイトトレーニングではないから毎日していい」というものがありますが、これは誤りです。 ●超回復理論により適切な休息期間をあけるべき筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、自重トレーニングもやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ■筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ筋肉の超回復に関する記載 ■全身の筋肉部位名称と作用筋トレで鍛える全身の筋肉部位は、その連動性・共働関係から以下のようにグループ分けでき、それぞれの筋肉の主な作用は以下の通りです。 ●上半身プレス系の筋肉・大胸筋:腕を前に押し出し閉じる・三角筋:腕を上・前・横・後ろに上げる・上腕三頭筋:肘を伸ばす・前腕伸筋群:手首を伸ばす ●上半身プル系の筋肉・僧帽筋:腕を下から引き上げる・広背筋:腕を上・前から引き寄せる・上腕二頭筋:肘を曲げる・前腕屈筋群:手首を曲げる ●体幹周辺の筋肉・腹筋群:体幹を屈曲・回旋させる・長背筋群:体幹を伸展:回旋させる・腸腰筋群:脚を前に上げる・臀筋群:脚を後ろに上げる ●下半身の筋肉・大腿四頭筋:膝を伸ばす・大腿二頭筋:膝を曲げる・下腿三頭筋:足首を伸ばす・前脛骨筋:足首を曲げる なお、さらに詳しい筋肉の名称と作用は以下の筋肉名称図鑑をご参照ください。 ▼筋肉名称図鑑 【筋肉の名前と作用の完全図鑑】筋トレ部位の名称と共働筋・拮抗筋|その鍛え方...
【自重トレーニングメニュー】限界突破の最強筋肥大筋トレの一週間の組み方
大胸筋・背筋・腕などの基本的な自重トレーニングメニューを解説するとともに、限界を突破して筋肥大するための負荷のかけ方や適切な回数設定の方法もご紹介します。あわせて、一週間の効果的なプログラムの組...