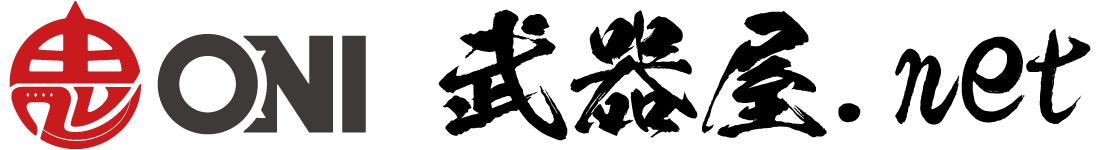Blog

【広背筋の鍛え方完全版】自重・ダンベル・チューブでの自宅筋トレからジムでの筋トレまで解説
広く男らしい逆三角形の体型になるためには、広背筋を鍛えなくてはいけません。その鍛え方を、自宅で行う自重・ダンベル・チューブトレーニングからご紹介するとともに、ジムで行うバーベルやマシンを使った広背筋の鍛え方まで完全解説します。 ■当サイト筋トレ情報のエビデンス(根拠)筋トレに関するネット情報はさまざまですが、当サイトでは下記の公的サイトの情報に基づき記載をしております。 ▼身体活動・運動の重要性について 厚生労働省「eヘルスネット|身体活動・運動」 ■広背筋の構造と作用●広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:こうはいきん英語名称:latissimus dorsi muscle部位詳細:上部|下部起始:下位第6胸椎~第5腰椎の棘突起・肩甲骨下角第9~12肋骨|正中仙骨稜・腸骨稜後方停止:上腕骨小結節稜 ●上半身最大の筋肉で前や上から腕を引く作用がある広背筋は上半身でも最大の筋肉で、上腕の付け根から腰にかけて逆三角形に広く分布しています。 その主な作用は、前や上から上腕を引くことです。上から腕を引く動作では広背筋の側部が強く関わり、前から腕を引く動作では広背筋の中央部が強く関わります。■筋繊維の種類と筋トレの反復回数筋力トレーニングの対象となる骨格筋は筋繊維が束となって構成されていますが、その筋繊維には主に速筋と遅筋の二種類があり、さらに速筋は2つのタイプに分けられます。そして、それぞれに特性が異なり、トレーニングでの適正反復回数も異なります。 ①遅筋(筋繊維タイプⅠ)1分以上の持久的な運動において、持続的に収縮する筋繊維です。トレーニングをしても筋肥大は起こらず、筋スタミナが向上します。筋トレにおいては20回の反復で限界がくるような軽負荷でトレーニングを行います。 ②速筋(筋繊維タイプⅡa)30~60秒程度のやや持久要素もある瞬発運動において、持続的かつ瞬発的に収縮する筋繊維です。トレーニングによってやや筋肥大するとともに筋スタミナも向上します。筋トレにおいては12~15回程度の反復で限界がくるような中負荷でトレーニングを行います。 ③速筋(筋繊維タイプⅡb)30秒未満の瞬発運動において、爆発的に収縮する筋繊維です。トレーニングによって強く筋肥大します。筋トレにおいては6~12回程度の反復で限界がくるような高負荷でトレーニングを行います。 骨格筋を構成している筋繊維には大きく分けて速筋と遅筋の2種類があります。速筋は白っぽいため白筋とも呼ばれます。収縮スピードが速く、瞬間的に大きな力を出すことができますが、長時間収縮を維持することができず張力が低下してしまいます。遅筋は赤みがかった色から赤筋とも呼ばれます。収縮のスピードは比較的遅く、大きな力を出すことはできませんが、疲れにくく長時間にわたって一定の張力を維持することができます。 ▼厚生労働省公式ページ 骨格筋(こっかくきん) ■広背筋を鍛える自重トレーニング●広背筋側部に効果的な懸垂広背筋側部を鍛える筋トレの王道とも言えるのが懸垂です。ノーマル懸垂はとくに側部に効果が高いので「逆三角形ボディー」を目指すならば、ぜひともトレーニングに組み込みたい種目です。 動作のポイントは、胸を張り上を見ながら身体を引き上げること、身体を引き上げたときに肩甲骨を寄せて広背筋を完全収縮させることです。 ●広背筋中央部に効果的なパラレル懸垂広背筋でも中央部に効果の高い懸垂が、グリップを平行にして行うパラレル懸垂です。動作のポイントは通常の懸垂とほぼ同様です。 また、どうしても自宅に懸垂する環境が作れないという方は、机を利用した斜め懸垂でもある程度は広背筋を鍛えることが可能です。 斜め懸垂(インバーテッドロー)は、懸垂ができない方や、背筋トレーニングのアップとして最適な種目です。胸を張り、肩甲骨を寄せるイメージで、腕の力ではなく背筋で動作をするようにしてください。 また、器具類がなくても、この画像のように机を流用して行うことも可能です。 ■広背筋を鍛えるチューブトレーニング●広背筋側部に効果的なチューブラットプル①上から腕を引くことで鍛えられるのが広背筋側部ですが、トレーニングチューブを利用して擬似的にその動作を再現し、広背筋側部を効果的に鍛えられるのが動画のようなチューブラットプルです。腕を引いた時にできるだけチューブを引き広げるのがポイントです。 ●広背筋側部に効果的なチューブラットプル②トレーニングチューブを使って広背筋側部を鍛えるやり方は他にもあります。壁にトレーニングチューブの一端を取り付けてラットプルを行うことでも可能です。 ●広背筋中央部に効果的なチューブローイング広背筋中央部に効果的なチューブトレーニングがチューブローイングです。胸を張りやや上を見ること、肘を開かずに行うのこと、引ききった時に肩甲骨をしっかり寄せることがポイントです。 上半身を傾けすぎると負荷が背筋群からそれてしまいますので、上半身は90度程度に維持し、胸を張って肩甲骨を寄せながら腕を引いてください。 ●広背筋中央部に効果的なチューブベントオーバーロー広背筋のなかでも中央部に効果的なチューブトレーニングがチューブベンチオーバーローです。筋トレの基本スタイルであるニーベントスタイルで行います。 なお、ニーベントスタイルは①胸を張る②背中を反らせる③お尻を突く出す④上を見る⑤膝をつま先より前に出さない、というのがポイントで、多くの筋トレで必要な基本フォームですので、この機会に習得しておくとよいでしょう。 ●広い可動域で広背筋側部に効果的なチューブワンハンドローイングこちらがチューブワンハンドローイングの模範的な動画です。 本種目の最大のメリットをいかし、できるだけ大きな動きで広背筋を最大伸展・最大収縮させてください。 また、腕を引きながら肩甲骨を寄せていき、最後に肩甲骨を寄せきって広背筋を完全収縮させることがポイントです。...
【広背筋の鍛え方完全版】自重・ダンベル・チューブでの自宅筋トレからジムでの筋トレまで解説
広く男らしい逆三角形の体型になるためには、広背筋を鍛えなくてはいけません。その鍛え方を、自宅で行う自重・ダンベル・チューブトレーニングからご紹介するとともに、ジムで行うバーベルやマシンを使った広...


【腕のバーベルトレーニング】上腕三頭筋・二頭筋それぞれの鍛え方・筋トレ方法
上腕三頭筋を部位別=長頭・短頭(内側頭・外側頭)にバーベルで鍛える筋トレ方法を解説します。太く形のよい上腕三頭筋を作るためには、部位ごとの特性を理解してトレーニングすることが大切です。 ■上腕の部位分けと作用●上腕三頭筋・上腕二頭筋・上腕筋に分けられる上腕はその位置と主な作用により3つの部位に分けられます。それは以下の通りです。 ①上腕三頭筋:上腕後面に位置する筋肉で、長頭・内側頭・外側頭の三部位から構成され、肘を伸展させる作用を持つ ②上腕二頭筋:上腕前面に位置する筋肉で、長頭・短頭から構成され、肘を屈曲・回外させる作用を持つ ③上腕筋:肘関節基部付近に位置し肘を屈曲させる作用を持つ ■上腕三頭筋のバーベル筋トレ●ナローグリップベンチプレス上腕三頭筋の基本となるバーベル筋トレがナローグリップ(クローズグリップ)ベンチプレスです。 肘を閉じ気味に動作を行えば長頭に、開き気味に動作を行えば短頭に効果的です。 いずれの場合も、三角筋に負荷が逃げないように、しっかりと肩甲骨を寄せて行うのがポイントです。 ●シーテッドフレンチプレス上腕三頭筋のなかで唯一肩甲骨に接合している上腕三頭筋長頭の特性上、シーテッドフレンチプレスのように肩より肘を上に上げて行う種目は、上腕三頭筋長頭が完全伸展から収縮するので、この部位を集中的に鍛えるのに適しています。 肩関節を動かすと、負荷が大胸筋や背筋群に逃げてしまいますので、しっかりと肘を固定して行ってください。 ●ライイングトライセプスエクステンションライイングトライセプスエクステンションは、動作が安定しやすく、肘関節から先だけに意識を集中させやすい種目です。 やや肘を開いて上腕三頭筋短頭をターゲットにするのに適しています。 ■上腕三頭筋を効果的に鍛えるグッズ●トライセプスバーの使用がおすすめ上腕三頭筋のトレーニングに、是非おすすめしたいのが、ハンマーグリップでバーベルを保持できるトライセプスバーで、特に上腕三頭筋長頭に有効です。 ●トライセプスバーエクステンションこちらは、トライセプスバーを使用したトライセプスエクステンションの動画です。 効率的に負荷を上腕三頭筋に集中させることが可能です。 ●トライセプスバーフレンチプレスまた、トライセプスバーを使ったフレンチプレスは、上腕三頭筋長頭を効率的に鍛えることができます。 ■上腕二頭筋のバーベルトレーニング●バーベルカール上腕二頭筋の基本的なバーベルトレーニングがバーベルカールです。反動を使わないように上腕二頭筋に意識を集中して行ってください。 ●バーベルドラッグカールまた、バーベルカールの途中に肘を引く動作を入れて、コンパウンド種目化したものがバーベルドラッグカールです。より高負荷で上腕二頭筋を鍛えることが可能です。 ●バーベルリバースカール上腕二頭筋の共働筋であり、肘関節の屈曲に対して大きなウエイトを占める上腕筋を鍛えるのに最適なバーベル種目がバーベルリバースカールです。副次的に前腕筋群にも効果があります。 ●リバースインクラインバーベルカールリバースインクラインバーベルカールは、インクラインベンチにうつ伏せになって行うことから「リーバース」の名称がついていますが、バーベルのグリップはリバースグリップではなくノーマルグリップです。 最大のメリットは前腕骨を床に対して垂直にすることができないので、肘を完全に曲げて上腕二頭筋を完全収縮させたポジションでも負荷がかかり続けることです。 なお、肘を伸ばした時に完全に伸ばしきることをせず、負荷を逃さないようにしてください。 ●バーベルプリチャーカル反動を使いにくくし、よりストリクトに上腕二頭筋を追い込めるバーベルカールのバリエーションが、カール台を使ったプリチャーカルです。 まず、カール台に肘を乗せ、バーベルを上の位置で構えます。そして、肘が動かないようにしっかりと固定してバーベルを下ろしていきますが、この時にゆっくりとコントロールした動作でエキセントリック収縮による負荷を与えてください。 次に、肘が完全に伸展する少し手前までバーベルを下ろしたら折り返し、バーベルを上げていきます。完全に上げきると前腕骨が床に対して垂直になり、負荷が筋肉から抜けてしまいますので、その直前でまたバーベルを下ろしていきます。 カール台を使えば、反動が完全になくなるかと言えばそんなことはなく、上半身を後ろに倒すことで反動が使えてしまいます。これを防ぐために大切なポイントが「足を肘より前に出さない」ことで、後ろに足を置くことで重心が前傾になり、身体を後ろに倒しにくくなります。 ●アームブラスターカールカール台のないジムや、自宅でバーベルカールを行う場合に、プリチャーカールに近い感覚で、反動を抑えてストリクトに上腕二頭筋を追い込める方法が「アームブラスター」や「アームプレート」と呼ばれるカール専用補助器具を使用したバリエーションです。 ▼関連記事【アームブラスター】反動筋トレさようなら|上腕二頭筋を鍛える優良グッズ ■部位別のバーベルトレーニング大胸筋のバーベルトレーニング背筋群のバーベルトレーニング三角筋のバーベルトレーニング上腕のバーベルトレーニングバーベルトレーニング完全解説
【腕のバーベルトレーニング】上腕三頭筋・二頭筋それぞれの鍛え方・筋トレ方法
上腕三頭筋を部位別=長頭・短頭(内側頭・外側頭)にバーベルで鍛える筋トレ方法を解説します。太く形のよい上腕三頭筋を作るためには、部位ごとの特性を理解してトレーニングすることが大切です。 ■上腕の...

【三角筋・肩のバーベルトレーニング】前部・中部・後部それぞれの鍛え方・筋トレ方法
肩の筋肉・三角筋のバーベルでの鍛え方を、全体・前部・中部・後部の部位別にそれぞれ効果的な種目を解説します。 ■三角筋の構造と作用三角筋は、前面、側面、後面の三部位にわけられます。それぞれ腕を、前に上げる、横に上げる、後ろに上げる働きをしています。また、全ての部位が共働して腕を上へ押し出す作用を持っています。 ○三角筋前部:腕を前に上げる○三角筋側部:腕を横に上げる○三角筋後部:腕を後ろに上げる ■三角筋の筋トレの負荷回数設定●まずは1セット15回で慣れれば8回筋トレをして筋肉を太く強くする場合にターゲットにする筋繊維は、速筋と呼ばれる瞬発的な動作をする筋繊維です。速筋にはFGタイプ(筋繊維TYPE2b)とFOタイプ(筋繊維TYPE2a)とがあり、それぞれに最適な負荷と反復回数は、前者で8~10回、後者で15回前後で限界がくる重さです。 なお、初心者の方は、まず15回で限界がくる負荷設定で鍛え始め、慣れてくればより高負荷の10回で限界がくる重量設定で鍛えるのがおすすめです。 ※三角筋は小さな筋肉なので、8回以下の高負荷設定で鍛えることはあまりおすすめしません。 ■三角筋全体のバーベルトレーニング●バーベルショルダープレスこちらが、基本となるスタンディングバーベルショルダープレスの模範的な動画です。まず、足を肩幅程度にとって安定させ、バーベルシャフトが鎖骨上に来るように構えます。 そこからバーベルを頭上に押し上げていきますが、三角筋は体幹の大きな筋肉である大胸筋や背筋群と隣接しているので、反動を使うと負荷が逃げてしまうという特性があります。 このため、反動は使わずに直立したまま押し上げられる重量設定で行います。また、バーベルを押し上げる動作のなかで三角筋前部・中部に負荷がかかり、ウエイトに耐えながら下ろす時に三角筋後部に負荷がかかります。 バーベルを押し上げる時だけでなく、下ろす時にもしっかりとコントロールしてエキセントリック収縮(伸張性収縮)による負荷を、しっかりと三角筋後部に加えてください。 また、セット終盤の追い込みの方法として、膝の屈伸を使って頭上にバーベルを差上げておき、下ろす時に耐えるネガティブ動作を数回追加するやり方があります。 バーベルショルダープレスでもっとも気をつけたいのが肘の位置です。肘が横から見て体幹より後ろになってしまうポジションになると、肩関節に対して強度の開き負荷がかかってしまいます。これは、多くの場合、セット終盤で苦しくなり上半身をのけぞらせるようなフォームになった時に起こります。 セット中は、肘が後ろにならないように常に意識して動作を行ってください。 ●バーベルショルダープレスのバリエーション・シーテッドバーベルショルダープレス三角筋の前部と中部に効果のあるバーベル筋トレがバーベルショルダープレスです。首の後ろにバーベルを下ろすビハインドネックと呼ばれるやり方もありますが、肩関節の柔軟性が必要ですので、まずはこの動画のようなフロントスタイルから始めることをおすすめします。 ・ミリタリープレス(バックショルダープレス)首の後ろにバーベルシャフトを下ろすバリエーションのショルダープレスは、米軍で好んで行われることからミリタリープレスの別名があります。 メリットとして、ウエイトに耐えながらネガティブ動作でバーベルを下ろす時に、鍛えるのが難しい三角筋後部に負荷がかかる特性があります。 ただし、本種目を安全に行うためには肩関節の柔軟性が必要で、身体の固い方が無理に行うと、肘が体幹ラインよりも後ろになってしまい、肩関節に対して強度の開き負荷がかかってしまうというリスクがあります。 本種目をやってみて肩関節に痛みを感じる場合はすぐに中止し、まずはストレッチなどで上半身の柔軟性を養っていくことをおすすめします。 ■三角筋前部のバーベルトレーニング●バーベルフロントレイズバーベルフロントレイズは両手でウエイトを保持できるので、ダンベルに比べると高重量でトレーニングができるというメリットがあります。 反面、反動を使ってしまいがちですので、完全にコントロールできる重量設定で行ってください。 ■三角筋中部のバーベルトレーニング●バーベルアップライトローイングこちらが、バーベルアップライトローイングの模範的な動画です。三角筋は体幹の大きな筋肉(大胸筋や背筋群)に隣接しており、負荷が体幹に逃げやすいため、やや効かせるのが難しいのですが、このバーベルアップライトローは初心者でも簡単に三角筋を追い込むことができる種目です。 最大の注意点は背中を後ろに傾ける反動を使わないことです。反動を使うと三角筋ではなく僧帽筋に刺激と負荷が逃げてしまいます。 ■三角筋後部のバーベルトレーニング●バーベルリアデルタローイングバーベルで三角筋後部を鍛えるのなら、バーベルリアデルタローイングがおすすめです。一見、ベントオーバーローイングのように見えますが、ベントオーバーローイングよりも引く位置が高く、また、完全に肘を開いて動作する点で異なります。 動画のような動作ができるように、かなり軽い重量設定で行わないと、背筋群のトレーニングになってしまいますので注意してください。 ■部位別のバーベルトレーニング大胸筋のバーベルトレーニング背筋群のバーベルトレーニング三角筋のバーベルトレーニング上腕のバーベルトレーニングバーベルトレーニング完全解説
【三角筋・肩のバーベルトレーニング】前部・中部・後部それぞれの鍛え方・筋トレ方法
肩の筋肉・三角筋のバーベルでの鍛え方を、全体・前部・中部・後部の部位別にそれぞれ効果的な種目を解説します。 ■三角筋の構造と作用三角筋は、前面、側面、後面の三部位にわけられます。それぞれ腕を、前...

【背中のバーベルトレーニング】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋それぞれの鍛え方・筋トレ方法
背中のバーベルトレーニングを、広背筋・僧帽筋の筋肉部位別に詳しく解説するとともに、脊柱起立筋を鍛える筋トレ方法もご紹介します。 ■背中の筋肉・背筋群の構造と作用まず、理解したいのが背中の筋肉・背筋群の構造です。背筋を構成している筋肉には大きく三つあり、それは、広背筋(脇から腰にかけての筋肉)、僧帽筋(首の後ろの筋肉)、脊柱起立筋(脊椎沿いの筋肉)です。 広背筋には「前や上から腕を引く」働きがあり、僧帽筋には「下から腕を引く」働きがあります。また、長背筋は脊柱起立背筋などの脊椎周辺のインナーマッスルの総称で「背筋を伸ばし維持する」働きがあります。 ●広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:こうはいきん英語名称:latissimus dorsi muscle部位詳細:上部|下部起始:下位第6胸椎~第5腰椎の棘突起・肩甲骨下角第9~12肋骨|正中仙骨稜・腸骨稜後方停止:上腕骨小結節稜 ●僧帽筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:そうぼうきん英語名称:trapezius muscle部位詳細:上部|中部|下部起始:後頭骨上項線・外後頭隆起・頚椎棘突起|第7頚椎・第1~3胸椎棘突起|第4~12胸椎棘突起停止:肩甲棘・肩峰 ●長背筋群・脊柱起立筋の英語名称・構造・部位詳細読みかた:せきちゅうきりつきん英語名称:erector spinae muscle部位詳細:腸肋筋|最長筋|棘筋長背筋群=脊柱起立筋+多裂筋+回旋筋など ■背筋のバーベルトレーニングの順番●高重量複合関節種目から低重量単関節種目へ背筋のバーベルトレーニングに限ったことではありませんが、筋トレの基本的な順番は高重量複合関節種目から低重量単関節種目へ、というのが定石です。具体的には、以下のような順番でセットをこなしていくとよいでしょう。①バーベルデッドリフト→②バーベルベントオーバーローイング→③バーベルショルダーシュラッグ→④バーベルグッドモーニング ■背筋のバーベルトレーニングの重量設定●筋肥大なら10回以内ダイエットなら20回以上の反復回数で背筋は高負荷に対して耐性が高いので、筋肥大目的で背筋のバーベルトレーニングを行う場合は、10回以内の反復回数で限界がくるような重量設定で行うのが一般的です。 また、引き締めダイエットや肩こり解消筋トレ目的で行う場合は、筋肥大しないように20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で行ってください。 なお、脊柱起立筋を鍛えるバーベルグッドモーニングは、インナーマッスルに対するトレーニングですので、高負荷で行うことは無意味なだけでなく腰椎故障の原因になります。必ず20回以上の反復ができる軽めの重量設定で行うようにしてください。 それでは、次の項目では具体的な背筋バーベル筋トレメニューをご紹介します。 ■背中全体のバーベルトレーニング●バーベルデッドリフトデッドリフトには数多くのバリエーションがありますが、主に二つのスタイルが主流で、それはヨーロピアンスタイルとスモウスタイルです。背中のトレーニングとして行う場合は、より背筋群の動員率の高いヨーロピアンスタイルがおすすめです。 ヨーロピアンスタイルのデッドリフトは、コンベンショナルデッドリフトとも呼ばれ、肩幅程度に開いた両足の外側をグリップするやり方です。 このスタイルは、背筋を使う比率が高いため、単にデッドリフトを背筋トレーニングとして行うのであれば、ヨーロピアンスタイルのほうがおすすめです。 また、日本人選手には少ないですが、特に手の長い欧米選手のなかには、こちらのスタイルで試合・試技を行う方もいます。 ヨーロピアンデッドリフトの正しいフォームを示したのがこちらの画像ですが、そのポイントは、胸を張ること、尻を突き出すこと、背中は真っ直ぐかやや反らせること、膝がつま先より前に出ないこと、上を見ることです。 このようなフォームを維持し、床からバーベルを引き上げていきますが、その軌道はできるだけ体幹に近く、すらわち、脛と腿をこすりながら上げるのが正しいやり方です。 また、引き上げたバーベルを床に戻すときは、尻を斜め後方に(椅子に座るように)移動させることが大切です。 デッドリフトは高重量で爆発的に背筋を鍛える反面、間違ったフォームで行うと腰椎や膝関節に爆発的な負担がかかります。 「背中を丸めない」「膝を突き出さない」の二点だけは、常に忘れず意識してください。 スモウスタイルのデッドリフトは、高重量を狙うパワーリフターに多用されるバリエーションで、大きく開いた両足の内側をグリップすることをが特徴です。 このスタイルは、背筋だけでなく半分近くは下半身の筋力で挙上を行います。このため、トレーニングの組み方として下半身のトレーニングとの兼ね合いが難しく、リフティング目的以外の一般的なトレーニーにはあまりおすすめしません。 やり方・フォームのポイント、胸・背中・尻の位置関係や挙上軌道は、先ほどのヨーロピアンスタイルに準じますが、膝とつま先の関係には特別に注意が必要です。 膝がつま先より前に出ないことは基本ですが、スモウスタイルではつま先の向きと膝の向きとを同じにすることが非常に重要です。 具体的には、スモウスタイルのデッドリフトでは、つま先を外に向けて開きますが、動作中は膝を常につま先と同じ向きにする意識を保ってください。...
【背中のバーベルトレーニング】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋それぞれの鍛え方・筋トレ方法
背中のバーベルトレーニングを、広背筋・僧帽筋の筋肉部位別に詳しく解説するとともに、脊柱起立筋を鍛える筋トレ方法もご紹介します。 ■背中の筋肉・背筋群の構造と作用まず、理解したいのが背中の筋肉・背...

【大胸筋のバーベルトレーニング】上部・下部・内側・外側+胸郭を広げる鍛え方
大胸筋のバーベルトレーニングを、基本となるベンチプレスを中心として上部・下部・内側・外側の部位別種目とそのやり方を解説するとともに、胸郭を広げるための筋トレ方法まで徹底的にご紹介します。 ■大胸筋の構造と作用●大胸筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止大胸筋は非常に面積の広い筋肉で、大きくは上部・下部・内側・外側に分けられます。腕を斜め上に押し出す時には上部が、斜め下に押し出す時には下部が、腕を開閉するときには外側と内側がそれぞれ主体となって働きます。このことを意識してトレーニングを行うとより効果的です。 ○大胸筋上部:腕を斜め上方に押し出す○大胸筋下部:腕を斜め下に押す出す○大胸筋内側:腕を前で閉じる○大胸筋外側:腕を横から閉じる ■大胸筋の筋トレの負荷回数設定●まずは1セット15回で慣れれば8回筋トレをして筋肉を太く強くする場合にターゲットにする筋繊維は、速筋と呼ばれる瞬発的な動作をする筋繊維です。速筋にはFGタイプ(筋繊維TYPE2b)とFOタイプ(筋繊維TYPE2a)とがあり、それぞれに最適な負荷と反復回数は、前者で8~10回、後者で15回前後で限界がくる重さです。 なお、初心者の方は、まず15回で限界がくる負荷設定で鍛え始め、慣れてくればより高負荷の8回で限界がくる重量設定で鍛えるのがおすすめです。 ■大胸筋全体のバーベル筋トレ●バーベルベンチプレスこちらがバーベルベンチプレスの模範的な動画です。まず、ベンチに仰向けになり、肩甲骨をしっかりと寄せて構えます。軽くブリッジを作り、肩甲骨2点とお尻のあわせて3点で上半身を支え、さらに足を踏ん張って計5点で全身を支えます。 こちらが、肩甲骨を寄せて上半身を支えるフォームと、肘と手首の位置関係をあらわした模式図です。常に手首の真下に肘があるように動作し、バーベルの重量は前腕骨で支え、それを肩甲骨で受け止めるイメージで動作を行います。 また、肩甲骨を固定したら、下半身で上半身を押し込むように力を入れ、ブリッジを作ります。これにより、全身が安定するとともに下半身の力も上半身へ伝えることが可能になります。 ラックからバーベルを外したら、肩甲骨の寄せが緩まないように気をつけながらみぞおちの真上までバーベルを移動させ、そこから筋力でコントロールしながら下ろしていきます。 胸にバーベルシャフトがついたらバーベルを押し上げますが、この時に肩甲骨を寄せたまま押し始めることに意識を集中してください。 この意識ができていないと、肩から先行して動くフォームになってしまい、肩関節に大きな負荷がかかるので注意が必要です。 トレーニングとしてバーベルベンチを行う場合には、完全に肘が伸びるポジションまでバーベルを押し上げる必要はなく、やや肘が曲がり筋肉に対する負荷が抜けない位置(肘を伸ばしてロックしない位置)で折り返すようにします。 なお、一般的な筋トレでは「力を入れながら息を吐く」ことが基本ですが、バーベルベンチプレスにおいては息を吸い込んだまま呼吸を止めて、胸郭を広げて行う呼吸方法がやりやすいでしょう。 ●フロアーベンチプレスベンチ類がなく、バーベルセットだけある環境では、床に直接仰向けになりベンチプレスを行うフロアーベンチプレスで通常のベンチプレスと同様の効果を得ることができます。 実は下半身の力が全く使えないため、通常のベンチプレスよりも強度が高く、国内の格闘技関係では「寝差し」と呼ばれ、上半身の高負荷トレーニングとして行われています。 なお、力尽きたときに危険ですので、直径の十分ある20kgプレートを使うようにしてください。 ■大胸筋上部のバーベル筋トレ●インクラインベンチプレスこちらが、模範的なインクラインバーベルベンチプレスの動画です。 肩甲骨を寄せて構え、バーベルをラックアウトしたら胸の真上まで移動させます。そして、筋力でコントロールしながら胸までシャフトを下ろし、その後に真上にバーベルを押し上げます。 最大のポイントは「肩甲骨を完全に寄せきったまま動作する」ことで、これができていないと肩関節に強い負荷がかかってしまい痛めるリスクがありますので、十分に注意してください。 また、インクラインバーベルベンチプレスは、最後まで尻を浮かせないことも非常に重要です。セット終盤で苦しいからと尻を浮かせてバーベルを押し上げると、せっかくの大胸筋上部に効果のある「斜め上方に腕を押し出す軌道」が失われ、通常のフラットベンチプレスとあまり変わらなくなってしまいます。 最後まで、しっかりとシートに尻をつけるようにしてください。 ●リバースグリップベンチプレスこちらが、リバースグリップベンチプレスの模範的な動画です。リバースグリップのままラックアウトすると、バランスが崩れて危険なため、まずはノーマルグリップでラックアウトし、いったんバーベルを胸に下ろします。 そこでグリップをリバースに握り直してから挙上動作に入ります。なお、補助者がいる場合はラックアウトの時点でリバースグリップでもかまいません。 リバースグリップベンチプレスのポイントは、脇を開かないことで、あまり脇を開くと負荷が分散するだけでなく、手首に強い捻れ負荷がかかりますので、十分に注意してください。 また、肩甲骨を寄せていないと肩にも負担がかかるため、セット中は肩甲骨のロックを外さないようにすることも重要です。 ■大胸筋下部のバーベル筋トレ●デクラインベンチプレスデクラインバーベルベンチプレスの模範的な動画がこちらになります。仰向けになり、肩甲骨を寄せ、肩甲骨2点と尻の合計3点で上半身を支えて構えます。 バーベルをラックから外したら胸の真上まで移動し、そこから筋力で支えてコントロールしながら胸に下ろします。そして、そこから真上にバーベルを押し上げます。 セット中は常に肩甲骨を寄せたままの状態を維持し、肩から初動しないように注意してください。 デクラインバーベルベンチプレスはセット終盤で苦しくなってきたときに、軽く尻を浮かせてセルフ補助することも可能で、このチーティングを上手に使うとより効率的に追い込むことも可能ですが、重量を追求するあまりどこまでも尻を浮かせることになりがちですので、あくまでも「効かせるための尻浮き」という意識を忘れないことが大切です。 ■大胸筋内側のバーベル筋トレ●クローズグリップベンチプレスナローベンチプレス(クローズグリップベンチプレス)の模範的な動画がこちらです。仰向けになり、肩甲骨を寄せて構えますが通常のベンチプレスほどブリッジは意識する必要はありません。...
【大胸筋のバーベルトレーニング】上部・下部・内側・外側+胸郭を広げる鍛え方
大胸筋のバーベルトレーニングを、基本となるベンチプレスを中心として上部・下部・内側・外側の部位別種目とそのやり方を解説するとともに、胸郭を広げるための筋トレ方法まで徹底的にご紹介します。 ■大胸...