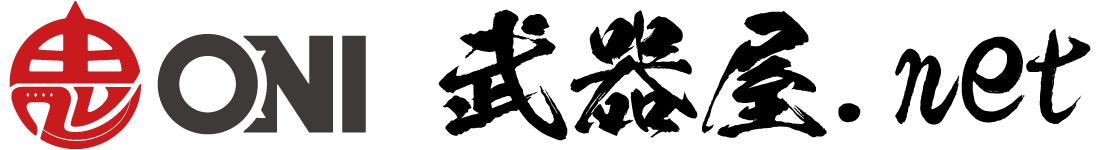肩の筋肉・三角筋のバーベルでの鍛え方を、全体・前部・中部・後部の部位別にそれぞれ効果的な種目を解説します。
■三角筋の構造と作用

三角筋は、前面、側面、後面の三部位にわけられます。それぞれ腕を、前に上げる、横に上げる、後ろに上げる働きをしています。また、全ての部位が共働して腕を上へ押し出す作用を持っています。
○三角筋前部:腕を前に上げる
○三角筋側部:腕を横に上げる
○三角筋後部:腕を後ろに上げる
■三角筋の筋トレの負荷回数設定
●まずは1セット15回で慣れれば8回

筋トレをして筋肉を太く強くする場合にターゲットにする筋繊維は、速筋と呼ばれる瞬発的な動作をする筋繊維です。速筋にはFGタイプ(筋繊維TYPE2b)とFOタイプ(筋繊維TYPE2a)とがあり、それぞれに最適な負荷と反復回数は、前者で8~10回、後者で15回前後で限界がくる重さです。
なお、初心者の方は、まず15回で限界がくる負荷設定で鍛え始め、慣れてくればより高負荷の10回で限界がくる重量設定で鍛えるのがおすすめです。
※三角筋は小さな筋肉なので、8回以下の高負荷設定で鍛えることはあまりおすすめしません。
■三角筋全体のバーベルトレーニング
●バーベルショルダープレス
こちらが、基本となるスタンディングバーベルショルダープレスの模範的な動画です。まず、足を肩幅程度にとって安定させ、バーベルシャフトが鎖骨上に来るように構えます。
そこからバーベルを頭上に押し上げていきますが、三角筋は体幹の大きな筋肉である大胸筋や背筋群と隣接しているので、反動を使うと負荷が逃げてしまうという特性があります。
このため、反動は使わずに直立したまま押し上げられる重量設定で行います。また、バーベルを押し上げる動作のなかで三角筋前部・中部に負荷がかかり、ウエイトに耐えながら下ろす時に三角筋後部に負荷がかかります。
バーベルを押し上げる時だけでなく、下ろす時にもしっかりとコントロールしてエキセントリック収縮(伸張性収縮)による負荷を、しっかりと三角筋後部に加えてください。
また、セット終盤の追い込みの方法として、膝の屈伸を使って頭上にバーベルを差上げておき、下ろす時に耐えるネガティブ動作を数回追加するやり方があります。
バーベルショルダープレスでもっとも気をつけたいのが肘の位置です。肘が横から見て体幹より後ろになってしまうポジションになると、肩関節に対して強度の開き負荷がかかってしまいます。これは、多くの場合、セット終盤で苦しくなり上半身をのけぞらせるようなフォームになった時に起こります。
セット中は、肘が後ろにならないように常に意識して動作を行ってください。
●バーベルショルダープレスのバリエーション
・シーテッドバーベルショルダープレス

三角筋の前部と中部に効果のあるバーベル筋トレがバーベルショルダープレスです。首の後ろにバーベルを下ろすビハインドネックと呼ばれるやり方もありますが、肩関節の柔軟性が必要ですので、まずはこの動画のようなフロントスタイルから始めることをおすすめします。
・ミリタリープレス(バックショルダープレス)

首の後ろにバーベルシャフトを下ろすバリエーションのショルダープレスは、米軍で好んで行われることからミリタリープレスの別名があります。
メリットとして、ウエイトに耐えながらネガティブ動作でバーベルを下ろす時に、鍛えるのが難しい三角筋後部に負荷がかかる特性があります。
ただし、本種目を安全に行うためには肩関節の柔軟性が必要で、身体の固い方が無理に行うと、肘が体幹ラインよりも後ろになってしまい、肩関節に対して強度の開き負荷がかかってしまうというリスクがあります。
本種目をやってみて肩関節に痛みを感じる場合はすぐに中止し、まずはストレッチなどで上半身の柔軟性を養っていくことをおすすめします。
■三角筋前部のバーベルトレーニング
●バーベルフロントレイズ
バーベルフロントレイズは両手でウエイトを保持できるので、ダンベルに比べると高重量でトレーニングができるというメリットがあります。
反面、反動を使ってしまいがちですので、完全にコントロールできる重量設定で行ってください。
■三角筋中部のバーベルトレーニング
●バーベルアップライトローイング
こちらが、バーベルアップライトローイングの模範的な動画です。三角筋は体幹の大きな筋肉(大胸筋や背筋群)に隣接しており、負荷が体幹に逃げやすいため、やや効かせるのが難しいのですが、このバーベルアップライトローは初心者でも簡単に三角筋を追い込むことができる種目です。
最大の注意点は背中を後ろに傾ける反動を使わないことです。反動を使うと三角筋ではなく僧帽筋に刺激と負荷が逃げてしまいます。
■三角筋後部のバーベルトレーニング
●バーベルリアデルタローイング
バーベルで三角筋後部を鍛えるのなら、バーベルリアデルタローイングがおすすめです。一見、ベントオーバーローイングのように見えますが、ベントオーバーローイングよりも引く位置が高く、また、完全に肘を開いて動作する点で異なります。
動画のような動作ができるように、かなり軽い重量設定で行わないと、背筋群のトレーニングになってしまいますので注意してください。