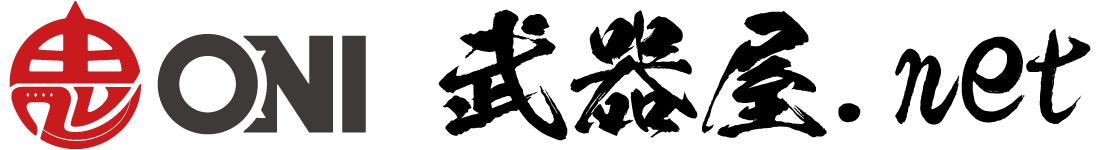Blog

大腿方形筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
大腿方形筋(Quadratus femoris muscle|だいたいほうけいきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 大腿方形筋の構造と作用大腿方形筋は坐骨に位置する深層筋で、股関節を外旋させる作用がある深層外旋六筋と呼ばれる筋肉群の一つです。大臀筋と協働関係にあります。 大腿方形筋(だいたいほうけいきん、quadratus femoris muscle)は人間の坐骨の筋肉で股関節の外旋を行う。 引用:Wikipedia「大腿方形筋」 大腿方形筋の鍛え方大腿方形筋だけをターゲットに鍛えられるトレーニング種目はありませんが、股関節外旋動作をともなうトレーニング種目のなかで表層筋と同時に刺激を加えることは可能です。 大腿方形筋が関与するトレーニング種目大腿方形筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。チューブアダクションダンベルワイドスクワットダンベルサイドランジマシンアダクションバーベルワイドスクワットバーベルサイドランジ 股関節の構造と周辺の筋肉股関節を構成する骨股関節は骨盤骨の窪みである寛骨臼に大腿骨の先端である大腿骨頭がはまるようにして構成されている球関節です。 また、股関節周辺には恥骨・脊椎骨(腰椎・仙堆・尾堆)が位置しています。 股関節(こかんせつ)は寛骨臼と大腿骨頭よりなる球関節(関節部分が球形(股関節の他に肩関節))であり、荷重関節(体重などがかかる関節(他に膝関節など))である。大腿骨頭は半球を上回る球形で、寛骨臼は深く大腿骨頭を収納するように形成され、大腿骨頭が容易に脱臼できない仕組みになっている。 引用:Wikipedia「股関節」 股関節周辺の筋肉股関節を構成している主たる筋肉(または周辺の筋肉)には、大腿直筋(大腿四頭筋)・腸腰筋群・内転筋群・臀筋群・大腿方形筋・縫工筋・梨状筋などがあります。 股関節周辺の筋肉の鍛え方腸腰筋群の作用と鍛え方内転筋群の作用と鍛え方臀筋群の作用と鍛え方大腿方形筋の作用と鍛え方縫工筋の作用と鍛え方 ▼詳細記事股関節の構造と周辺の筋肉 関連記事体幹インナーマッスル図鑑インナーマッスルの名称・作用と体幹トレーニングの実施方法については下記の記事をご参照ください。体幹インナーマッスルの名前と作用 筋肉の名称と作用の図鑑アウターマッスルの主な筋肉の名称・作用および筋力トレーニングの実施方法については、下記の記事をご参照ください。筋肉の種類・名称と作用|部位別の鍛え方 筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る 筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
大腿方形筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
大腿方形筋(Quadratus femoris muscle|だいたいほうけいきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 大腿方形筋の構造と作用大腿方形筋は坐骨に位置する深層筋...

臀筋群の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
臀筋(Gluteal muscles|でんきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 臀筋の構造と作用臀筋は、主に大臀筋・中臀筋・小臀筋の三層構造から構成されており、これに腸骨に接合する大腿筋膜張筋を加えた4つの筋肉を総称したものです。 それぞれの筋肉の持つ作用は以下のとおりです。 大臀筋:股関節伸展・股関節外旋・股関節外転・股関節内転 中臀筋:股関節外転・股関節内旋・股関節外旋 小臀筋:股関節外転・股関節内旋・股関節外旋 大腿筋膜張筋:股関節屈曲・膝関節伸展 なお、大臀筋は股関節伸展、中臀筋と小臀筋は股関節外転がもっとも強い作用となっています。 臀筋(でんきん)とは、臀部に存在する筋肉の総称である。 構成する筋肉 大臀筋 中臀筋 小臀筋 大腿筋膜張筋 引用:Wikipedia「臀筋」 詳しい大臀筋の情報大臀筋の構造・作用と鍛え方 詳しい中臀筋の情報中臀筋の構造・作用と鍛え方 詳しい小臀筋の情報小臀筋の構造・作用と鍛え方 臀筋の鍛え方臀筋のトレーニングは、主に最大の体積を持つ表層筋である大臀筋に対して実施され、股関節伸展(脚を後方に上げる)の動作をともなうトレーニング種目で鍛えられます。 臀筋が関与するトレーニング種目臀筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。 大臀筋ブルガリアンスクワットチューブレッグカールダンベルフロントランジダンベルスティッフレッグドデッドリフトダンベルレッグカールマシンレッグカールバーベルスティッフレッグドデッドリフトバーベルフロントランジ 中臀筋・小臀筋ワイドスクワットダンベルワイドスクワットダンベルサイドランジバーベルワイドスクワットバーベルサイドランジ 股関節の構造と周辺の筋肉股関節を構成する骨股関節は骨盤骨の窪みである寛骨臼に大腿骨の先端である大腿骨頭がはまるようにして構成されている球関節です。 また、股関節周辺には恥骨・脊椎骨(腰椎・仙堆・尾堆)が位置しています。 股関節(こかんせつ)は寛骨臼と大腿骨頭よりなる球関節(関節部分が球形(股関節の他に肩関節))であり、荷重関節(体重などがかかる関節(他に膝関節など))である。大腿骨頭は半球を上回る球形で、寛骨臼は深く大腿骨頭を収納するように形成され、大腿骨頭が容易に脱臼できない仕組みになっている。 引用:Wikipedia「股関節」 股関節周辺の筋肉股関節を構成している主たる筋肉(または周辺の筋肉)には、大腿直筋(大腿四頭筋)・腸腰筋群・内転筋群・臀筋群・大腿方形筋・縫工筋・梨状筋などがあります。 股関節周辺の筋肉の鍛え方腸腰筋群の作用と鍛え方内転筋群の作用と鍛え方臀筋群の作用と鍛え方大腿方形筋の作用と鍛え方縫工筋の作用と鍛え方 ▼詳細記事股関節の構造と周辺の筋肉...
臀筋群の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
臀筋(Gluteal muscles|でんきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 臀筋の構造と作用臀筋は、主に大臀筋・中臀筋・小臀筋の三層構造から構成されており、これに腸骨...

腕橈骨筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
腕橈骨筋(Brachioradialis muscle|わんとうこつきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 腕橈骨筋の構造と作用腕橈骨筋は前腕部外側に位置する前腕伸筋群のなかでも最大の筋肉で、肘関節屈曲と前腕回旋の作用を持っています。 腕橈骨筋(わんとうこつきん、brachioradialis muscle)は人間の腕の筋肉で肘関節の屈曲、前腕を回内回外位から半回内位に回旋を行う。 引用:Wikipedia「腕橈骨筋」 腕橈骨筋の鍛え方腕橈骨筋は、肘関節屈曲動作をともなうトレーニング種目のなかでも、手の平が向き合うグリップ(ハンマーグリップ)や手の平が下を向くグリップ(リバースグリップ)での種目で鍛えることが可能です。 また、リストハンマー・リストカール・リストスピネーションといった前腕トレーニング種目で集中的に負荷を加えることが可能です。 リストハンマー・リストカール・リストスピネーションの実施方法 腕橈骨筋が関与するトレーニング種目腕橈骨筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。▼動画つき解説 懸垂 斜め懸垂 チューブローイング チューブカール ダンベルローイング ダンベルハンマーカール ケーブルローイング ケーブルカール バーベルベントオーバーロー バーベルカール sfphes.orgより 肘関節の構造と周辺の筋肉肘関節を構成する骨肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成されており、それぞれ腕橈関節(上腕骨と橈骨)、腕尺関節(上腕骨と尺骨)、上橈尺関節(橈骨と尺骨)と呼ばれる3つの関節からできている複関節です。 肘関節(ちゅうかんせつ)は、肘にある関節。肘関節は上腕骨と橈骨、尺骨から成る関節であり複関節に分類される。蝶番関節としても分類される。 引用:Wikipedia「肘関節」 肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉肘関節は、前腕屈筋群に属する円回内筋・橈側手根屈筋・尺側手根伸筋・長掌筋・浅指屈筋、前腕伸筋群に属する長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・尺側手根伸筋・回外筋、および上腕伸筋群に属する肘筋から構成されています。 また、周辺の筋肉として上腕三頭筋・上腕二頭筋・上腕筋・肘筋があります。 肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉の鍛え方腕橈骨筋の作用と鍛え方長橈側手根伸筋の作用と鍛え方橈側手根屈筋の作用と鍛え方円回内筋の作用と鍛え方前腕筋群の作用と鍛え方肘筋の作用と鍛え方上腕筋の作用と鍛え方上腕二頭筋・三頭筋の作用と鍛え方 関連記事体幹インナーマッスル図鑑インナーマッスルの名称・作用と体幹トレーニングの実施方法については下記の記事をご参照ください。体幹インナーマッスルの名前と作用 筋肉の名称と作用の図鑑アウターマッスルの主な筋肉の名称・作用および筋力トレーニングの実施方法については、下記の記事をご参照ください。筋肉の種類・名称と作用|部位別の鍛え方 筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
腕橈骨筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
腕橈骨筋(Brachioradialis muscle|わんとうこつきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 腕橈骨筋の構造と作用腕橈骨筋は前腕部外側に位置する前腕伸筋群のな...

肘筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
肘筋( Anconeus muscle|ちゅうきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 肘筋の構造と作用肘筋は肘関節近くの外側に位置する筋肉で、肘関節を伸展させる作用を持っており、上腕三頭筋と協働して働きます。 また、肘関節屈曲時には肘関節の関節包がずれないように外側からサポートする働きも持ちます。 肘筋(ちゅうきん)は人間の上肢の筋肉。上腕骨の外側上顆後面上方から起こり、尺骨後面に停止する。支配神経は腕神経叢の後神経束の枝である橈骨神経である。作用としては肘関節の伸展を行う。伸展時には上腕三頭筋と共に協調して働く。 引用:Wikipedia「肘筋」 肘筋の鍛え方肘筋だけをターゲットに鍛えられるトレーニング種目はありませんが、肘関節の伸展動作をともなうトレーニング種目のなかで上腕三頭筋と同時に刺激を加えることは可能です。 特に、前腕の回内動作をともなう種目で強く刺激することができます。 肘筋が関与するトレーニング種目肘筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。ダイヤモンド腕立て伏せナロープッシュアップチューブプレスダウンチューブフレンチプレスチューブトライセプスエクステンションチューブキックバックダンベルトライセプスプレスダンベルフレンチプレスダンベルキックバックダンベルテイトプレスバーベルフレンチプレスケーブルプレスダウンローププレスダウン 肘関節の構造と周辺の筋肉肘関節を構成する骨肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成されており、それぞれ腕橈関節(上腕骨と橈骨)、腕尺関節(上腕骨と尺骨)、上橈尺関節(橈骨と尺骨)と呼ばれる3つの関節からできている複関節です。 肘関節(ちゅうかんせつ)は、肘にある関節。肘関節は上腕骨と橈骨、尺骨から成る関節であり複関節に分類される。蝶番関節としても分類される。 引用:Wikipedia「肘関節」 肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉肘関節は、前腕屈筋群に属する円回内筋・橈側手根屈筋・尺側手根伸筋・長掌筋・浅指屈筋、前腕伸筋群に属する長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・尺側手根伸筋・回外筋、および上腕伸筋群に属する肘筋から構成されています。 また、周辺の筋肉として上腕三頭筋・上腕二頭筋・上腕筋・肘筋があります。 肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉の鍛え方腕橈骨筋の作用と鍛え方長橈側手根伸筋の作用と鍛え方橈側手根屈筋の作用と鍛え方円回内筋の作用と鍛え方前腕筋群の作用と鍛え方肘筋の作用と鍛え方上腕筋の作用と鍛え方上腕二頭筋・三頭筋の作用と鍛え方 関連記事体幹インナーマッスル図鑑インナーマッスルの名称・作用と体幹トレーニングの実施方法については下記の記事をご参照ください。体幹インナーマッスルの名前と作用 筋肉の名称と作用の図鑑アウターマッスルの主な筋肉の名称・作用および筋力トレーニングの実施方法については、下記の記事をご参照ください。筋肉の種類・名称と作用|部位別の鍛え方 筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
肘筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
肘筋( Anconeus muscle|ちゅうきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 肘筋の構造と作用肘筋は肘関節近くの外側に位置する筋肉で、肘関節を伸展させる作用を持って...

上腕筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
上腕筋(Brachialis muscle|じょうわんきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 上腕筋の構造と作用上腕筋は肘関節内側に位置する筋肉で、上腕二頭筋・烏口腕筋と協働して肘関節を屈曲させる作用があります。 上腕筋(じょうわんきん)は人間の上肢の筋肉。上腕骨内側外側前面の下半分から起こり、尺骨粗面に停止する。 支配神経は腕神経叢の外側神経束の枝である筋皮神経であるが、外側部は後神経束由来の橈骨神経である。 作用としては肘関節の屈曲を行う。屈曲時には烏口腕筋、上腕二頭筋などと共に協調して働く。 引用:Wikipedia「上腕筋」 上腕筋の鍛え方上腕筋は、肘関節屈曲動作をともなうトレーニング種目のなかでも、手の平が向き合うグリップ(ハンマーグリップ)や手の平が下を向くグリップ(リバースグリップ)での種目で鍛えることが可能です。 上腕筋が関与するトレーニング種目上腕筋が関与するトレーニング種目は以下の通りです。 懸垂斜め懸垂チューブローイングチューブラットプルダウンダンベルローイングTバーローイングケーブルローイングラットプルダウンバーベルベントオーバーローイングチューブカールチューブハンマーカールダンベルカールダンベルハンマーカールダンベルコンセントレーションカールインクラインダンベルカールダンベルサイドカールマシンカールケーブルカールバーベルカール 肘関節の構造と周辺の筋肉肘関節を構成する骨肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成されており、それぞれ腕橈関節(上腕骨と橈骨)、腕尺関節(上腕骨と尺骨)、上橈尺関節(橈骨と尺骨)と呼ばれる3つの関節からできている複関節です。 肘関節(ちゅうかんせつ)は、肘にある関節。肘関節は上腕骨と橈骨、尺骨から成る関節であり複関節に分類される。蝶番関節としても分類される。 引用:Wikipedia「肘関節」 肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉肘関節は、前腕屈筋群に属する円回内筋・橈側手根屈筋・尺側手根伸筋・長掌筋・浅指屈筋、前腕伸筋群に属する長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・尺側手根伸筋・回外筋、および上腕伸筋群に属する肘筋から構成されています。 また、周辺の筋肉として上腕三頭筋・上腕二頭筋・上腕筋・肘筋があります。肘関節を構成する筋肉と周辺の筋肉の鍛え方腕橈骨筋の作用と鍛え方長橈側手根伸筋の作用と鍛え方橈側手根屈筋の作用と鍛え方円回内筋の作用と鍛え方前腕筋群の作用と鍛え方肘筋の作用と鍛え方上腕筋の作用と鍛え方上腕二頭筋・三頭筋の作用と鍛え方 関連記事体幹インナーマッスル図鑑インナーマッスルの名称・作用と体幹トレーニングの実施方法については下記の記事をご参照ください。体幹インナーマッスルの名前と作用 筋肉の名称と作用の図鑑アウターマッスルの主な筋肉の名称・作用および筋力トレーニングの実施方法については、下記の記事をご参照ください。筋肉の種類・名称と作用|部位別の鍛え方 筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る 筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
上腕筋の構造・作用と鍛え方(筋力トレーニング)
上腕筋(Brachialis muscle|じょうわんきん)の構造・作用およびトレーニング方法について解説します。 上腕筋の構造と作用上腕筋は肘関節内側に位置する筋肉で、上腕二頭筋・烏口腕筋と協...

【背中の自重トレーニング】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋の筋トレ方法
自重で背中の筋肉(広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋)を鍛える方法をご紹介するとともに、それぞれの種目の効果的な動作ポイントを解説します。 ■背中の筋肉・背筋群の構造と作用●広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋から構成される背筋は、表層筋である広背筋・僧帽筋と、脊柱沿いの深層筋(インナーマッスル)である脊柱起立筋から構成されていますが、それぞれ特徴と作用は以下の通りです。 ○広背筋:背面に逆三角形状に広く分布し、上半身で最大の筋肉です。腕を上や前から引く作用があります。鍛えることで逆三角形の体型になります。 ○僧帽筋:首の後ろから肩にかけて分布する筋肉で、腕を下~引くとともに肩甲骨を寄せる作用があります。鍛えることで横から見て分厚い上半身になります。 ○脊柱起立筋:脊椎沿いに分布するインナーマッスルの総称で、体幹を伸展させるとともに姿勢を維持する作用があります。鍛えることで体幹力が向上するとともに正しい姿勢になります。 ■背筋の筋トレの負荷回数設定●まずは1セット15回で慣れれば8回筋トレをして筋肉を太く強くする場合にターゲットにする筋繊維は、速筋と呼ばれる瞬発的な動作をする筋繊維です。速筋にはFGタイプ(筋繊維TYPE2b)とFOタイプ(筋繊維TYPE2a)があり、それぞれに最適な負荷回数設定は、前者で8~10回、後者で15回で限界がくる重さです。 初心者の方は、まず15回で限界がくる負荷設定で鍛え始め、慣れてくればより高負荷の8回で限界がくる重量設定で鍛えるのがおすすめです。 ■広背筋の自重トレーニング●懸垂(プルアップ)背筋自重トレーニングの王道とも言える種目がチンニングです。肩幅よりやや広く順手でバーを保持し行います。顎をバーより上に出すイメージだと背中が丸まりやすく、背筋よりも上腕や前腕に先に効いてしまうので、胸を張り、胸筋上部をバーにつけにいくイメージで動作を行ってください。 ※国内では懸垂のことを一般的にチンニングと呼称しますが、英語圏では正しくはプルアップと呼びます。 なお、握力がなくなってしまう人は、サムレスグリップでバーを保持するとよいでしょう。 ●斜め懸垂(インバーテッドロー)自宅にある机を流用した順手斜め懸垂(インバーテッドロウ)がこちらの動画のものです。肩幅よりやや広く手幅をとり、背すじを真っ直ぐに伸ばし、胸を張り肩甲骨を寄せながら身体を引き上げます。広背筋を中心に効果的です。 ■僧帽筋の自重トレーニング●パラレル懸垂この画像のように、両手が平行になるような握り方(パラレルグリップ)で懸垂を行うと、僧帽筋を中心に広背筋中央部に負荷が集中します。 また、この動画のように机を流用した斜め懸垂でも僧帽筋を鍛えることが可能です。 ●逆手懸垂(チンニング)バーを逆手(リバースグリップ)で握って行う逆手懸垂は、僧帽筋を中心として広背筋中央部や上腕二頭筋に効果があります。なお、肩甲骨をしっかりと寄せると僧帽筋に、あえて肩甲骨を寄せない動作で行うと上腕二頭筋に負荷がかかります。 ■脊柱起立筋の自重トレーニング●バックエクステンション こちらにご紹介している二つの動画が、手の位置に若干の違いはありますが、バックエクステンションのもっともスタンダードな自重でのやり方です。 強度で言えば、上の手を頭の上に置くバリエーションのほうが高負荷で男性向き、下の手を腰の近くに伸ばすバリエーションのほうが低負荷で女性向きです。 その動作のポイント・注意点や反復回数の目安および呼吸の方法などは以下の通りです。 ①長背筋群の筋収縮と首の連動性を考慮して「下を見ない」ことが大切です。下を見ながら動作を行っても長背筋群は最大収縮せず、適切の効果を得ることができません。前を見て動作を行ってください。 ②反動を使って反復を行うと、腰椎に強い負荷がかかり腰痛の原因になります。反動は使わず、ゆっくりとして動作を心がけてください。 ③バックエクステンションで鍛える長背筋群はインナーマッスルです。このため、一般的なアウターマッスルの筋トレとは違い、高負荷・低反復回数で鍛えることは不可能であるばかりでなく、怪我の原因になります。その反復回数の目安としては20レップ程度の高反復回数・低負荷で行うのが最適です。 ④筋肉は息を止めている時と吐く時に収縮し、息を吸うときに弛緩する特性があります。これはバックエクステンションにおいても例外ではなく、手足を持ち上げる時に息を吐き、手足を下ろしてから息を吸うのが正しい呼吸方法です。
【背中の自重トレーニング】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋の筋トレ方法
自重で背中の筋肉(広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋)を鍛える方法をご紹介するとともに、それぞれの種目の効果的な動作ポイントを解説します。 ■背中の筋肉・背筋群の構造と作用●広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋か...