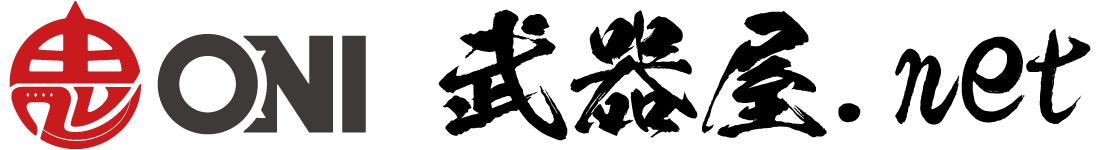リフティングシューズとは、かかとがつま先側に対して15mmから25mmほど高くなっており、靴を構成するアッパー素材や底材が硬く滑りにくい素材で構成され、ウエイトリフティング動作等の強い衝撃を受け止められる構造を有するシューズです。
さて、リフティングシューズといえど高さや足幅まで様々なモデルがあります。実は、メーカー側には明確な設計思想と使用用途が設定されていますが、使用用途について明確に記載されていることがほとんどありません。
そのため消費者は、ウエイトリフティング、クロスフィット、パワーリフティング、ボディビルディングにまで幅広く精通し、何足も自腹を切って試して来た方の意見を聞いて買うべきシューズをセレクトする必要がありました。
現在リフティングシューズを開発している事もあり、全日本パワーリフティング選手権大会で14回(2025年3月16日現在)の実績があり、数多くの自腹を切って経験豊富なアドバイザーとして小早川渉氏からの監修の基、リフティングシューズの分類と使用用途について明記します。
1A ウエイトリフティング専用のリフティングシューズ(一体型)

画像引用:MAX BARBELL LLC(https://www.maxbarbell.com/collections/weightlifting-shoes/products/luxiaojun-champion-powerpro-i-weightlifting-shoesgolden)
Adidas(アディダス):ADIPOWER(アディパワー)
NIKE(ナイキ):ROMALEOS(ロマレオス)
Reebok(リーボック): Legacy Lifter(レガシーリフター)
LUXIAOJUN(ルシャオジュン):ウエイトリフティングシューズ
ANTA:ウエイトリフティングシューズ
UNDER ARMOR(アンダーアーマー):レインリフター
SABO:パワーリフトPRO(※スクワットシューズを謳っていますが、構造上はウエイトリフティングシューズです。)
ウエイトリフティング専用のシューズは、足指回りが狭く、硬い素材でできており、傾斜が19mm-25mmと最も高い傾向にあります。また、ロマレオス、ルシャオジュン等靴底の剛性が高いシューズは、靴底にカーボンプレートが入っています。
ウエイトリフティングの着地の衝撃をしっかりと受け止た上で反発に変えるため柔らかい素材は一切使われておらず、つま先もあえて狭くして壁になるように設計されています。(※TYRのフォースワンのみ特許のワイドトゥを搭載しています。)
そして、ウエイトリフティングでキャッチした時に身体とバーベルの重心バランスが取れるよう計算された構造及び傾斜を有しています。
1B ウエイトリフティング専用のシューズ(セパレート型)

画像引用:アスポ アスリート(https://item.rakuten.co.jp/aspo/tp-1163a006-400/)
ASICS(アシックス):ウェイトリフティングシューズ
TYR(ティア):FORCE(フォースエリートカーボンリフター)
セパレート型はウエイトリフティング動作における曲げ対応能力が高く、キャッチの瞬間のスピードと衝撃によって靴底にしなりを発生させ、そのしなり戻りを反発に利用する特性があります。
2 クロスリフティング用(ウエイトリフティング・クロスフィット兼用)のリフティングシューズ

画像引用:MAX BARBELL LLC(https://www.maxbarbell.com/collections/weightlifting-shoes/products/luxiaojun-champion-powerpro-i-weightlifting-shoesgolden)
Reebok(リーボック):CROSS LITER(クロスフィットリフター)
TYR(ティア):L-1
TYR(ティア):L-2
NIKE(ナイキ):SAVALEOS(サバレオス)
SABO:ファーストリフトトレーナー
クロスリフティング用のシューズは、クロスフィット競技においてウエイトリフティング動作だけでなく、走ったり飛んだりも要求されるため屈曲性が良い、柔らかいもしくは薄いつま先であり、ヒールドロップはウエイトリフティング用と比較して低く、15mm-21mmが主流です。
ワイドトゥは機能性として、入門的なライトリフティングを想定し、快適性と安定性を重視しているからと推測されます。(※あくまでもシリアスな競技ウエイトリフティングと比較してです。)
リーボックアンバサーの小早川氏にウエイトリフティング専用のNIKE社のロマレオスというモデルとクロスリフティング用のTYR社のL-2というモデルの比較動画を見せてもらいましたが、全く異なります。全く異なる事がそもそも設計思想と使用用途が違うためこのようにそれぞれのシューズの分類が必要となり、消費者は適切に選択して購入する必要があります。
ロマレオスとL-2の違いはこちらの動画です。ぜひご参照ください。
リフティングシューズは、明確に使用用途が異なります。どのメーカーも明確に使用用途や向いていない動作について書いてくれていません。
そこで小早川さん監修の基、弊社がカテゴリー分けした内容を本日晩のメルマガで発表します。
本日中に間に合うかとサーバーエラーが起きないかが懸念事項です。 pic.twitter.com/LoZcI90saY
— 奥谷元哉 鬼の社長 (@okutani0706) March 2, 2025
ここまでお読みいただいたらウエイトリフティング専用シューズではつま先が硬すぎて走るのには向いていないと想像がつくのではないでしょうか。
各社のリフティングシューズは、明確に目的を持った設計をされており、明らかに最適な使用用途があります。それにも関わらず、本当に向いている用途やあまり向いていない用途については明確に記載されていない事が多く、ビジネスとしては幅広く売りたいのでしょう。
3 バックスクワット専用のリフティングシューズ
ここに現在開発中のSTK-1が入ります。
パワーリフティングのワールドゲームズで優勝経験があり、「現役の男子パワーリフティング選手」として現在実績No.1(※2025年3月16日執筆時点)の佐竹選手が市販のシューズでは本来のスクワットの実力が出せないという要望にお応えして開発が始まったバックスクワット専用シューズです。
開発中に素晴らしい知見を発見したため急遽特許を出願する事となりました。特許の内容につきましては、出願して世に公開します。
このバックスクワット用シューズは2025年現在最も廃れてしまったジャンルですが、弊社が全力で開発し、価値観のパラダイムシフトを発生させ、バックスクワット用シューズの基準となる製品を流通させます。
そもそもバックスクワット用シューズには始祖と言える存在があります。

画像引用:(https://uufcfa.dekhle.za.com/index.php?main_page=product_info&products_id=14232)
それがSAFE社のスクワット用シューズです。これは30代後半以上で2000年代からパワーリフティングをやっていた人達しか知らないシューズで、残念ながら今はもう製造されていません。
ウエイトトレーニングの偉人、チェーン、バンドトレーニングの始祖であり、ベルトスクワットやグルートハムレイズを生み出したかの有名なウエストサイドバーベルクラブの故ルイ・シモンズ氏は「バックスクワットにハイヒールは不要」と言い切り、コンバースのチャックテイラーが最高のリフティングシューズであると主張しました。 この流れをくむのがセーフスクワットシューズです。

コンバース チャックテイラー 画像引用:(https://kanverse.kr/products/m9160c)
しかしながら、2000年代初頭にスクワットスーツ等のギアの硬さが一気に増してしゃがみにくくなった事と、欧州人特有の足首の硬さもかち合ってしまい、足首の可動性を出すためにロシアやウクライナの選手を中心としてヒールの高いシューズが主流となりました。
さらに、より商品力やデザイン性に優れ、世界一のブランド力があるナイキ社がロマレオスを2008年に発売した事によりバックスクワットであってもヒールの高いシューズを使用する事が主流となりました。(※この時期のパワーリフティングは、フルギア(エクイップ)部門が主流でした。)
2018年あたりから強烈な回帰が起こり、ノーギア(クラシック)主流が決定的となりました。
回帰した事によりヒールが高すぎる弊害が目立つようになりました。そこでフランス代表チームのようにSAFEが主流だった頃に戻ったかのようにジョーダン1を代用する選手達も出てくるようになりました。
この流れにより、クラシックの選手はバックスクワットシューズの本流であるヒールの低いSAFEに戻るべきでしたが、時すでに遅しでSAFEの靴は廃盤となり、現在に至ります。
さらに、パワーリフティングのスクワットはウエイトリフティングの着地と比較して動作の速度が遅く、衝撃が弱いため着地のスピードと衝撃を利用した反発を使えないためセパレート型のシューズも向きません。つま先の不安定性とセパレート部分の沈み込みだけのマイナス作用が発生します。TYRのエリートカーボンリフターは、つま先からミッドフットまでカーボンを配置する事により剛性を高め、しなり戻りの反力を高めています。他のセパレート型よりトゥを含めた安定性が格段に良くなっていますが、そのカーボンによるミッドフットの剛性向上により、しゃがみ込みの際に沈むマイナス作用が強まっています。スクワットにおいては、一体型構造でカーボンプレートが搭載されたモデルにはしゃがみ込みの際の安定性、ボトムからの反発においては一歩かないません。
STK-1は、SAFEと同様の一体型構造、低いヒールドロップ、硬い素材を採用し、最新の仕様であるウルトラワイドトゥを搭載しています。
そして、特許出願の「とある要素」によりどのリフティングシューズよりもバックスクワット時にスムーズにバックステップができるようになっています。
これは、厚さ20mm以上の沈み込みが発生するゴムマットでスクワットをせざるを得ない24時間ジムの環境においても対沈み込み効果を発生し、足を取られにくくなり、地面反力も強まります。
佐竹選手の先週滋賀県で開催されたジャパンクラシックパワーでの日本記録255.5kgの映像ですが、この重量で軽やかなバックステップをご覧ください。従来品よりも明らかに軽くバックステップができるため特許を出願する事としました。
この投稿をInstagramで見る
パワーリフティングのスクワットに求められる3要素
パワーリフティングのスクワット(バックスクワット、ローバーバックスクワット)では以下の3要素が求められます。
1 バックステップをスムーズに行えること
パワーリフティングの公式大会では、スクワットの動作を行う前にラックから自力でバーベルを外し、バックステップを行い、ラックにバーが引っかからない位置までバックステップで移動した後静止し、審判のスタートのコールを待つ必要があります。
バックステップが決まらない事は他のスポーツではアドレス(構え)が決まらないと同じ意味であり、試技の成功確率を大きく下げます。逆にバックステップがスムーズに行える事は構えが容易に決まるため試技の成功確率が上がります。
高重量になるほどバックステップは難しく、シビアになり、ちょっとのズレで結果が大きく変わります。
2 規定の深さまでしゃがみやすいこと
パワーリフティングの公式大会では、大腿の臀部に対する付け根であるヒップジョイント部分が膝頭よりも下がる必要があります。1でも書きましたが、しゃがみやすさを求めてヒールの高さを上げる事は根本的には問題を解決していません。股関節、殿筋、足首周りの柔軟性、バーベルの乗せる位置、構え、しゃがみの意識を改善して本来解決すべき問題です。
ヒールの傾斜が上がると足首周りの柔軟性だけカバーできますが、背負ったバーベルの重心位置も上がるためローバースクワットではしゃがみにくい重心位置関係が発生します。
3 ボトムからの立ち上がりやすさ
ボトムから軽く立ち上がれる事が理想です。
弊社が開発したSTK-1は、この全てを兼ね備えています。残念ながらウエイトリフティングシューズやクロスリフティングシューズを流用した場合、この3要素のいずれかが欠けてしまいます。
論より証拠ですのでSTK-1と他のシューズを比較した動画を御覧ください。全日本パワーリフティング選手権大会で14回の優勝を重ねる小早川選手によるテストです。スクワットの技術力が日本トップクラスの選手でもこれだけ動きに違いが出ます。
この投稿をInstagramで見る
違いの解説
白色シューズ
TYRのL-2です。つま先にカーボン等の硬い素材を使用していないため屈曲性に優れているためバックステップが軽やかです。しかしながら、ボトムからの立ち上がり速度は明らかに遅いです。
黄色シューズ
NIKEのROMALEOS2です。つま先にカーボンプレートが搭載されているため屈曲性が悪く、バックステップの重く、引っかかりかけています。反面、ボトムからの立ち上がりはカーボンプレートの効果によりL-2と比較して明らかに速度が出ています。
黒色シューズ
ONIのSTK-1です。つま先にカーボンプレートを搭載していますが、特許構造により屈曲性を確保できているためバックステップが軽やかです。さらに、カーボンプレートの反発とウルトラワイドトゥによる安定性向上により、明らかに速い速度でボトムから立ち上がっています。
明確に分類化された今、使用用途に応じた最適なリフティングシューズを選択する
最初は特に分からなかったのでフラットシューズでスクワットを行っていて、しゃがみやすくなるからとウエイトリフティング専用シューズやクロスリフティング用シューズに切り替えてカーフ周辺に妙な張り感や腰の違和感を覚えた事はないでしょうか?それはあなたの体形やバーを乗せる位置、スクワットのフォームにそのシューズが合っていない明確な証拠です。
リフティングシューズは上述の通り、使用用途が明確に分かれます。違うシューズを使うという事はサッカーのスパイクで野球をするぐらいにズレた事をやってしまっています。
今まではハイヒール主流の流れがあった事やバックスクワット専用のローヒールシューズが流通されなくなった事により、足首周りの柔軟性が要求されるフラットシューズや使用用途の異なるリフティングシューズを流用せざるを得ない状況でしたが、STK-1が発売された後にはこのシューズがバックスクワット専用シューズの基準となります。
もう「使用用途の違う」シューズで無理していい感じにはまっていると自分に言い聞かせて使わなくても良くなります。
これはサンクコストという現象で、かけてしまった費用が回収できないにも関わらず進むのをやめられない状態です。リフティングシューズは高価であるがゆえにサンクコストが起こりやすい。
パワーリフティングのバックスクワット用にはONI STK-1が最適解
パワーリフティングやBIG3のスクワットに求められる全ての要素を兼ね備えているバックスクワット専用シューズはSTK-1です。STK-1の登場により、パワーリフティングのスクワットに最適なシューズを今後は選択できるようになります。
バックスクワット専用シューズSTK-1ですが、金型も全サイズ完成し、最終確認サンプル待ちで、5月の市販予想で進めています。
※本記事は、2025年3月3日15時に配信された武器屋.net内のメールマガジンを基に加筆修正した記事です。今後も情報が更新されましたら記事内容は更新されます。最新情報や奥深い業界の話、クーポンが配信されるメールマガジンの購読は、こちらをご参照いただきご登録ください。