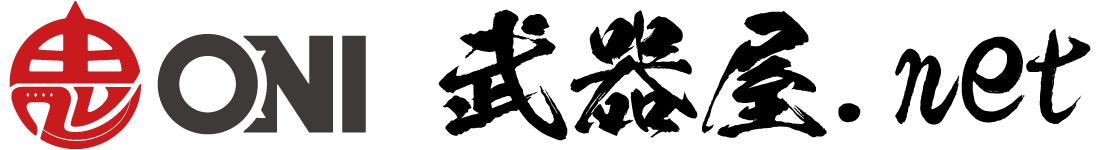背中のバーベルトレーニングを、広背筋・僧帽筋の筋肉部位別に詳しく解説するとともに、脊柱起立筋を鍛える筋トレ方法もご紹介します。
■背中の筋肉・背筋群の構造と作用

まず、理解したいのが背中の筋肉・背筋群の構造です。背筋を構成している筋肉には大きく三つあり、それは、広背筋(脇から腰にかけての筋肉)、僧帽筋(首の後ろの筋肉)、脊柱起立筋(脊椎沿いの筋肉)です。
広背筋には「前や上から腕を引く」働きがあり、僧帽筋には「下から腕を引く」働きがあります。また、長背筋は脊柱起立背筋などの脊椎周辺のインナーマッスルの総称で「背筋を伸ばし維持する」働きがあります。
●広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:こうはいきん
英語名称:latissimus dorsi muscle
部位詳細:上部|下部
起始:下位第6胸椎~第5腰椎の棘突起・肩甲骨下角第9~12肋骨|正中仙骨稜・腸骨稜後方
停止:上腕骨小結節稜
●僧帽筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:そうぼうきん
英語名称:trapezius muscle
部位詳細:上部|中部|下部
起始:後頭骨上項線・外後頭隆起・頚椎棘突起|第7頚椎・第1~3胸椎棘突起|第4~12胸椎棘突起
停止:肩甲棘・肩峰
●長背筋群・脊柱起立筋の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:せきちゅうきりつきん
英語名称:erector spinae muscle
部位詳細:腸肋筋|最長筋|棘筋
長背筋群=脊柱起立筋+多裂筋+回旋筋など
■背筋のバーベルトレーニングの順番
●高重量複合関節種目から低重量単関節種目へ
背筋のバーベルトレーニングに限ったことではありませんが、筋トレの基本的な順番は高重量複合関節種目から低重量単関節種目へ、というのが定石です。具体的には、以下のような順番でセットをこなしていくとよいでしょう。
①バーベルデッドリフト→②バーベルベントオーバーローイング→③バーベルショルダーシュラッグ→④バーベルグッドモーニング
■背筋のバーベルトレーニングの重量設定
●筋肥大なら10回以内ダイエットなら20回以上の反復回数で

背筋は高負荷に対して耐性が高いので、筋肥大目的で背筋のバーベルトレーニングを行う場合は、10回以内の反復回数で限界がくるような重量設定で行うのが一般的です。
また、引き締めダイエットや肩こり解消筋トレ目的で行う場合は、筋肥大しないように20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で行ってください。
なお、脊柱起立筋を鍛えるバーベルグッドモーニングは、インナーマッスルに対するトレーニングですので、高負荷で行うことは無意味なだけでなく腰椎故障の原因になります。必ず20回以上の反復ができる軽めの重量設定で行うようにしてください。
それでは、次の項目では具体的な背筋バーベル筋トレメニューをご紹介します。
■背中全体のバーベルトレーニング
●バーベルデッドリフト
デッドリフトには数多くのバリエーションがありますが、主に二つのスタイルが主流で、それはヨーロピアンスタイルとスモウスタイルです。背中のトレーニングとして行う場合は、より背筋群の動員率の高いヨーロピアンスタイルがおすすめです。
ヨーロピアンスタイルのデッドリフトは、コンベンショナルデッドリフトとも呼ばれ、肩幅程度に開いた両足の外側をグリップするやり方です。
このスタイルは、背筋を使う比率が高いため、単にデッドリフトを背筋トレーニングとして行うのであれば、ヨーロピアンスタイルのほうがおすすめです。
また、日本人選手には少ないですが、特に手の長い欧米選手のなかには、こちらのスタイルで試合・試技を行う方もいます。

ヨーロピアンデッドリフトの正しいフォームを示したのがこちらの画像ですが、そのポイントは、胸を張ること、尻を突き出すこと、背中は真っ直ぐかやや反らせること、膝がつま先より前に出ないこと、上を見ることです。
このようなフォームを維持し、床からバーベルを引き上げていきますが、その軌道はできるだけ体幹に近く、すらわち、脛と腿をこすりながら上げるのが正しいやり方です。
また、引き上げたバーベルを床に戻すときは、尻を斜め後方に(椅子に座るように)移動させることが大切です。
デッドリフトは高重量で爆発的に背筋を鍛える反面、間違ったフォームで行うと腰椎や膝関節に爆発的な負担がかかります。
「背中を丸めない」「膝を突き出さない」の二点だけは、常に忘れず意識してください。
スモウスタイルのデッドリフトは、高重量を狙うパワーリフターに多用されるバリエーションで、大きく開いた両足の内側をグリップすることをが特徴です。
このスタイルは、背筋だけでなく半分近くは下半身の筋力で挙上を行います。このため、トレーニングの組み方として下半身のトレーニングとの兼ね合いが難しく、リフティング目的以外の一般的なトレーニーにはあまりおすすめしません。
やり方・フォームのポイント、胸・背中・尻の位置関係や挙上軌道は、先ほどのヨーロピアンスタイルに準じますが、膝とつま先の関係には特別に注意が必要です。
膝がつま先より前に出ないことは基本ですが、スモウスタイルではつま先の向きと膝の向きとを同じにすることが非常に重要です。
具体的には、スモウスタイルのデッドリフトでは、つま先を外に向けて開きますが、動作中は膝を常につま先と同じ向きにする意識を保ってください。
内股になったりガニ股になったりすると、非常に強い捻れ負荷が膝にかかりますので、かなり危険です。
スモウスタイルのデッドリフトに挑戦する方は、事前に軽い重量でフォーム練習を十分に行ってからチャレンジしましょう。
●デフィシットデッドリフト

デフィシットデッドリフトは、台の上に乗ることで、さらに深いレンジまでしゃがみこんで鍛えることのできるバリエーションで、パワーリフターの方が好んで行うやり方です。
ただし、深くしゃがみこんだポジションで主に負荷がかかるのは下半身の筋肉ですので、背筋のトレーニングとしてデッドリフトに取り組む一般的なトレーニーの方には、あまり必要のないバリエーションです。
●ハーフデッドリフト

ハーフデッドリフト(ブロックデッドリフト)は、パワーラックや台を利用してフルレンジのデッドリフトの上半分だけを反復するバリエーションで、トップサイドデッドリフトとも呼ばれます。
下半身に多くの負荷がかかるデッドリフトの下半分の動作をあえて省くことで、背筋群だけにトレーニングを集中させることができます。
特に、下半身のトレーニングは背筋のトレーニングと分けたい、一般的なトレーニーにおすすめの方法です。
●バーベルベントオーバーローイング
こちらが、一般的なバーベルベントオーバーローイングの動画で、手の甲が上になる状態=リバースグリップで行います。
このバリエーションでは、広背筋に対してかかる負荷が大きくなり、手幅を広くすると広背筋側部に、手幅を狭くすると広背筋中央部に効果的です。

バーベルベントオーバーローイングは、「ニーベントスタイル」と呼ばれる筋トレの基本フォームで構えて行いますが、そのポイントは、胸を張りやや背中を反らせ、尻を突き出し膝がつま先より前に出ないように構えることです。
また、背筋の収縮と首の連動性を考慮して「顎を上げる」ことも大切です。
動作のポイントとして重要なのは、バーベルの重心ができるだけ体幹から離れないようにすることで、具体的には太ももの上を擦りながら引き上げる軌道で動作します。
●バーベルベントオーバーローイングのバリエーション
・イェーツローイング

こちらの画像は、かのミスターオリンピア・ドリアンイェーツ氏が考案した、別名イェーツローイングとも呼ばれるバリエーションです。
一般的なバーベルベントオーバーローイングとの相違点は、あまり腰と膝を曲げない構え方で、シャフトがヘソより上で往復するように動作する点です。
このフォームによるメリットは二つあり、一つが「腰に負担が少ないこと」で、もう一つが「上背部を集中的に鍛えられる」ことです。
・ベンチローイング

こちらの画像は、ベンチローイングと呼ばれるバリエーションで、ベンチにうつ伏せになり完全に体重をあずけることで、腰への負担がほぼフリーとなるやり方です。また、腕を引く軌道が前方からとなりますので、広背筋に特に有効です。
■広背筋のバーベルトレーニング
●ストレートアームバーベルプルオーバー
こちらが広背筋を狙ったバーベルプルオーバーの模範的な動画です。大胸筋ねらいのベントアームスタイルに対して「ストレートアーム」プルオーバーと呼ばれ、肘を伸ばして大きく開いて行うことが特徴です。
なお、背筋群と首の連動性を考慮し「顎を上げて」動作を行うことが重要です。
ストレートアームバーベルプルオーバーを行う上で、リスク回避のために必ず留意していただきたいのが、万が一セット中に力尽きたとしても、肩関節の可動範囲内でバーベルが落下する環境で行うということです。
具体的には、高さ(直径)のある20kgプレートを使ったり、後方に台を設置したり、補助者をつけたりというのが対処方法です。
■僧帽筋のバーベルトレーニング
●バーベルショルダーシュラッグ
僧帽筋を集中的に鍛えることのできるバーベル筋トレがバーベルショルダーシュラッグです。
動作のポイントは肩甲骨を寄せきってから、さらに僧帽筋を収縮させてバーベルを引き上げることです。フィニッシュポジションでやや顎を上げると僧帽筋が完全収縮し、さらに効果が高まります。
■脊柱起立筋のバーベルトレーニング
●バーベルグッドモーニング
バーベルグッドモーニングの模範的な動画がこちらです。首よりもやや下、僧帽筋に乗せるようにバーベルを担ぎ、名称の由来でもある「おはようございます」とおじぎをするように上半身を前に倒していきます。
なだし、そのまま真っ直ぐに前に上半身を倒すと、バランスを失って転倒のリスクや腰を痛める危険性があります。尻を突き出すようにするとともに、顔を上げ前を向いて動作をすることが重要です。
また、腰椎への負担を避けるため、上半身を倒すのは床と並行までにとどめ、折り返し点では反動を使わないように注意してください。

バーベルグッドモーニングの動作ポイントを簡単に言えば「身体の重心を移動させない」ことです。
当然、上半身を大きく前に倒す種目ですので、そのままだと身体の重心は前方へ移動してしまいます。これを避けるために、スタビライザーのように尻を後方に突き出し、重心が移動することを防ぎます。
また、背中を丸めると腰椎にとって非常にハイリスクですので、背すじを伸ばす、または、やや反らせるイメージを持って動作を行ってください。