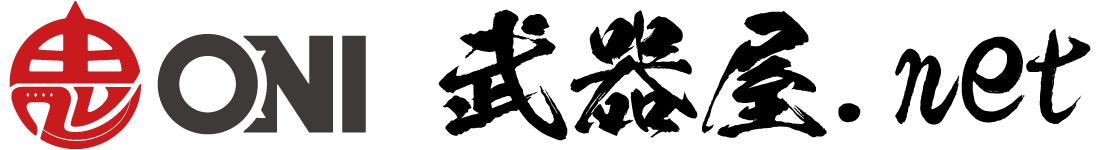Blog

【大胸筋のチューブトレーニング】胸の仕上げ筋トレを上部・下部・内側の部位別に解説
大胸筋のチューブトレーニングは、腕立て伏せなどの自重トレーニングやダンベルプレスなどのダンベル筋トレの後の仕上げ・追い込みトレーニングとして非常に有効なトレーニング方法です。 そのやり方を大胸筋の部位別(上部・下部・内側)に動画をまじえてご紹介します。 チューブトレーニングは動作のあいだ常に筋肉に負荷がかかり続けるとともに、伸びれば伸びるほど負荷が増加する漸増負荷という特性があるので、大胸筋を最大収縮させるのにも効果的です。 ■大胸筋の構造と作用●大胸筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止読みかた:だいきょうきん英語名称:pectoralis major muscle部位詳細:上部|中部(内側)|下部●上部・下部・内側に分けられ腕を押し出し閉じる作用がある大胸筋は、上部・下部・内側に分けられ、その作用は以下のようになります ○大胸筋上部:腕を斜め上方に押し出す作用があります。 ○大胸筋下部:腕を斜め下方に押し出す作用があります。 ○大胸筋内側:腕を前方で閉じる作用があります。 ■チューブトレーニングの効果を上げる方法チューブトレーニングの効果を上げるためには、トレーニングチューブの特性、チューブ筋トレの特徴をしっかりと把握して取り組む必要があります。 ①自重筋トレやダンベルトレーニングと組み合わせるチューブトレーニングはそれ単体で行うよりも、まずは高負荷で筋肉を刺激することのできる自重トレーニングやダンベルトレーニングの複合関節種目(複数の筋肉と関節を同時に使う種目)を行った後に、追い込みや仕上げとして行うことで効果を高めることができます。 ②筋肉の伸展時に負荷が抜けないように構える各トレーニング種目での筋肉の伸展ポジションで、トレーニングチューブがたるんで負荷が完全に抜けてしまうと筋トレ効果が落ちてしまいます。必ず、筋肉の伸展時にもテンションがかかるようにトレーニングチューブをセットして構えてください。 ③漸増負荷特性を意識して筋肉を最大収縮させるトレーニングチューブはゴムの持つ「伸びるほど負荷が増加する」という「漸増負荷特性」を利用することで、効率的な筋トレを実現することが可能です。ゴムのテンションを感じながら、しっかりとターゲットにした筋肉を完全収縮するようにしてください。 ④筋トレ目的に合わせたチューブの強度設定をする筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2bおよそ10秒以内の短時間に瞬発的な収縮をし、鍛えると強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a30~60秒ほどの持続的かつ瞬発的な収縮をし、鍛えると程よく筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上の持久的な収縮をし、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。20回以上の反復回数で限界がくる重さの設定で鍛えます。 つまり、バルクアップ目的なら①、細マッチョや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。 チューブトレーニングの場合は、チューブ自体の強度の選定・チューブの張り方などで調整するほか、必要に応じて複数本のトレーニングチューブを束ねて使用してください。 ■超回復とは筋肉は筋トレによって負荷を受けると、筋繊維が破壊されます。そして、回復する時に、負荷を受ける前よりも強くなって回復する能力が備わっており、これを「超回復」と呼びます。 この超回復という筋肉の特性を利用し、定期的に筋トレによって意図的に筋繊維を破壊し、筋肉を強くしていくのが「筋トレと超回復」の基本理論です。 よく「超回復理論は証明されていない」と言う記載もありますが、公的機関のホームページにもしっかりと記載されていますので、筋トレはやはり超回復理論にのっとって行うことが大切です。 ●筋トレ(無酸素運動)と超回復理論に関する公的情報”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)” ▼厚生労働省公式ページ 筋肉の超回復に関する記載 ■推奨されるトレーニングチューブトレーニングチューブにはさまざまな製品がありますが、執筆者の運営するジムで実際に使用し、また運営ショップで取り扱っているのがこちらのタイプです。 最大の特徴は、一般的なタイプに比べて大型のカラビナフックが付属していることで、ケーブルマシン用の各種アタッチメントなど幅広いグリップ・ハンドルが装着できることです。 また、仲介業者を介さず工場から直接仕入れをしているため、リーズナブルに提供できています。 このトレーニングチューブを見る ▼関連記事おすすめトレーニングチューブと筋肥大効果のある使い方|トレーナーが本音で解説...
【大胸筋のチューブトレーニング】胸の仕上げ筋トレを上部・下部・内側の部位別に解説
大胸筋のチューブトレーニングは、腕立て伏せなどの自重トレーニングやダンベルプレスなどのダンベル筋トレの後の仕上げ・追い込みトレーニングとして非常に有効なトレーニング方法です。 そのやり方を大胸筋...

【背中のダンベル筋トレメニュー】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋それぞれの鍛え方
背中のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■背中の筋肉の構造と作用●広背筋の構造と作用広背筋は上側部と中央部~下部に部位分けされます。広背筋には上や前から腕を引き寄せる作用があり、手幅が広い順手で腕を引くと広背筋上側部に、手幅が狭い逆手で腕を引くと広背筋中央部~下部に負荷がかかります。 Wikipediaによる記載広背筋(こうはいきん)は、背部の筋肉の棘腕筋のうち、下方に三角形をなす筋肉である。 チンニング(懸垂)がもっともよく知られており効果も高いが、たいていの人間には負荷が高すぎる。その場合には、ラットプルダウン、ベント・オーバー・ローイング、ロープーリーなどの各種目が存在する。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/広背筋 ●僧帽筋の構造と作用僧帽筋は上部・中部・下部の三部位に分けられます。僧帽筋の作用は肩甲骨を寄せることで、上から腕を引く動作では僧帽筋下部が、前から腕を引く動作では僧帽筋中部が、下から腕を引く動作では僧帽筋上部がそれぞれ作用します。 Wikipediaによる記載僧帽筋(そうぼうきん、英語: trapezius)は、人間の背中の一番表層にある筋肉である。 上方の筋線維は肩甲骨を持ち上げ、中間付近の筋線維は内側に引っ張り、下方の筋線維は下に下げ、上方と下方の筋線維が両方収縮するときは回転させる。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/僧帽筋 ●脊柱起立筋の構造と作用脊柱起立筋は背骨沿いの筋肉群である長背筋の一部で、棘筋・最長筋・腸肋筋の三つの筋肉から構成されています。体幹を伸展させる作用を持つとともに、姿勢の維持にも働いています。 Wikipediaによる記載脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)は、長背筋のうち、脊柱の背側に位置する筋肉である。脊柱起立筋のうち、外側の筋群を腸肋筋、中間内側の筋群を最長筋、最内側の筋群を棘筋とよぶ。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/脊柱起立筋 ■背中のダンベル種目一覧(動画つき解説)ダンベルローイングワンハンドローイングダンベルショルダーシュラッグダンベルデッドリフトダンベルプルオーバーダンベルリバースフライダンベルグッドモーニング ■筋トレ目的別の負荷重量設定筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2b約10秒前後の短い時間に爆発的・瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a10~60秒ほどのやや長時間で瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングによりやや筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上数分・数時間の持続的・持久的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより筋肥大せずに筋密度が上がります。20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 つまり、筋肥大バルクアップ目的なら①、細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、減量引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。ただし、腹筋郡・前腕筋郡・下腿三頭筋など日常での使用頻度が高い部位は、基本的に20回以上高反復回数で鍛えます。 ■背中全体の代表的ダンベル種目●ダンベルデッドリフトこの図は、ストレートレッグダンベルデッドリフトと呼ばれるやり方で、ダンベルデッドリフトのなかではもっとも一般的な膝をあまり曲げないバリエーションです。 僧帽筋と脊柱起立背筋に効果的なやり方で、胸を張り、お尻をやや突きだして、上を見ながら動作を行うのがポイントです。背中は常に反らした状態を保ってください。背中が丸まると腰椎を痛める原因になります。 【本種目のやり方とフォームのポイント】 ①胸を張って背すじを真っ直ぐにし、腕を伸ばしてダンベルを持って構える ②膝がつま先よりも前に出ないように注意し、お尻を突き出して前傾姿勢を作りながらダンベルを床に下ろしていく ③ダンベルを床に着く直前まで下ろしたら、同じ軌道で立ち上がりながらダンベルを引き上げていく ④ダンベルを引き上げたら、肩甲骨をしっかりと寄せて背筋群を完全に収縮させる ■広背筋の代表的ダンベル種目●ダンベルワンハンドローイングワンハンドダンベルローイングはベンチなどに片手をついて行うダンベルローイングの一バリエーションで、自身の姿勢を100%支える必要がないので、高重量のダンベルを引き上げることに集中できるのが大きなメリットです。胸を張り、やや顎を上げて行うのは、ローイング系種目の基本と同じです。 また、本種目はダンベルローイングのバリエーションのなかで、もっとも広背筋の可動範囲が広くなりますので、広背筋をターゲットにする場合におすすめの種目で、特に広背筋中央部に効果的です。 なお、可動域の広さを最大限活かすためには、体幹のひねり動作をともなって、できるかぎり大きな動作で行うことが重要になります。 【本種目のやり方とフォームのポイント】...
【背中のダンベル筋トレメニュー】広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋それぞれの鍛え方
背中のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■背中の筋肉の構造と作用●広背筋の構造と作用広背筋は上側部と...

【大胸筋のダンベル筋トレメニュー】上部・内側・下部それぞれの鍛え方
胸の筋肉・大胸筋のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(上部・内側・下部)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■大胸筋の構造と作用●上部・内側・下部から構成される大胸筋は上部・内側・下部の三部位に分けられます。それぞれの主な作用は以下の通りです。 大胸筋上部:腕を斜め上方に押し出す大胸筋内側:腕を前方で閉じる大胸筋下部:腕を斜め下方に押し出す Wikipediaによる記載大胸筋(だいきょうきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうち、鎖骨、胸骨と肋軟骨(第2~第7前面)、腹直筋鞘の3部を起始とし、上外方に集まりながら、上腕骨の大結節稜に停止する。 大胸筋を鍛える筋力トレーニング法には多くの種目が存在する。最も手軽で一般的なのはプッシュアップ(腕立て伏せ)であり、バーベルを使ったベンチプレス、ダンベルを使ったダンベル・フライなどもよく知られている。身体前面に位置し、もっとも目立つ筋肉の一つであることからボディビルなどでは重要視される筋肉の一つ。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/大胸筋 ■大胸筋のダンベル種目一覧(動画つき解説)ダンベルプレスダンベルフロアープレスダンベルインクラインプレスダンベルデクラインプレスダンベルフライダンベルインクラインフライダンベルデクラインフライ ■筋トレ目的別の負荷重量設定筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。 ①速筋繊維TYPE2b約10秒前後の短い時間に爆発的・瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ②速筋繊維TYPE2a10~60秒ほどのやや長時間で瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングによりやや筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 ③遅筋繊維TYPE160秒以上数分・数時間の持続的・持久的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより筋肥大せずに筋密度が上がります。20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。 つまり、筋肥大バルクアップ目的なら①、細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、減量引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。ただし、腹筋郡・前腕筋郡・下腿三頭筋など日常での使用頻度が高い部位は、基本的に20回以上高反復回数で鍛えます。 ■大胸筋全体の代表的種目●ダンベルプレスダンベルプレスは、大胸筋全体に効果があります。また、二次的に三角筋と上腕三頭筋にも効果的です。 ダンベルプレスは、常に手首の真下に肘がくるように動作するのが、効率的に大胸筋に負荷をかけるポイントです。この位置関係がずれてしまうと負荷が三角筋や腕に逃げてしまいます。 また、構えるときは肩甲骨を寄せ軽くブリッジを組み、肩甲骨のトップ二箇所と臀部の合計三点で身体を支えるようにします。 【本種目のやり方とフォームのポイント】 ①ベンチに仰向けになり、肩甲骨をしっかりと寄せ、胸の上にダンベルを上げて構える ②肩甲骨を寄せたまま、ダンベルを下ろしていきますが、肩のラインよりも頭側には下ろさないように注意する ③ダンベルをできるだけ深く下ろしたら、肩甲骨を寄せたまま、腰を浮かせないように注意してダンベルを押し上げる ④ダンベルを押し上げたら、軽く顎を引いて大胸筋を完全に収縮させる ダンベルプレスは、肩関節よりも頭側にダンベルを下ろすと肩関節を怪我しますので注意してください。また、できるだけ深くダンベルを下ろすことが重要で、浅いダンベルプレスはダンベルトレーニング最大のメリットである「可動域が広く筋肉を最大伸展できる」ということを活用できていないということになりますので、可能なかぎり深くダンベルを下ろしてください。 ■大胸筋上部の代表的種目●インクラインダンベルプレスインクラインダンベルプレスは、大胸筋のなかでも上部に効果があります。また、二次的に三角筋と上腕三頭筋にも効果的です。 この種目は、斜め上方への軌道により大胸筋上部に効果の高いトレーニングですが、セット終盤で苦しくなって腰を浮かせてしまうと、その軌道が通常のダンベルプレスと変わらなくなりますので、最後まで腰をベンチにつけて動作を行ってください。 【本種目のやり方とフォームのポイント】 ①インクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨をしっかりと寄せ、胸の上にダンベルを上げて構える ②肩甲骨を寄せたまま、ダンベルを下ろしていきますが、肩のラインよりも頭側には下ろさないように注意する ③ダンベルをできるだけ深く下ろしたら、肩甲骨を寄せたまま、腰を浮かせないように注意してダンベルを押し上げる ④ダンベルを押し上げたら、軽く顎を引いて大胸筋上部を完全に収縮させる ●インクラインダンベルフライインクラインダンベルフライは、大胸筋の上部内側を鍛えるのに効果的なダンベルトレーニングです。ポイントはフィニッシュポジションでダンベルを押し上げる意識をして大胸筋を最大収縮させることです。また、この時にやや顎を引くようにするとさらに効果は高まります。 【本種目のやり方とフォームのポイント】...
【大胸筋のダンベル筋トレメニュー】上部・内側・下部それぞれの鍛え方
胸の筋肉・大胸筋のダンベルを使った鍛え方を、筋肉の部位別(上部・内側・下部)のそれぞれに、代表的な筋トレメニューを厳選して解説します。 ■大胸筋の構造と作用●上部・内側・下部から構成される大胸筋...

【上腕三頭筋長頭の鍛え方】上腕筋群中で競技に最重要と言われる理由と筋トレ方法
上腕三頭筋長頭(一番体側の部位)は上腕筋群のなかでも、競技能力向上に最重要と言われています。その理由と、実際に筆者の運営しているジムで実践および指導している鍛え方のポイントを厳選してご紹介します。 執筆者(上岡岳)プローフィール【アームレスリング主戦績】全日本マスターズ80kg超級2位アジア選手権マスターズ90kg級3位 ■上腕筋を構成する筋肉●上腕二頭筋・上腕三頭筋・上腕筋上腕部のアウターマッスルには上腕二頭筋・上腕三頭筋・上腕筋および三角筋があります。 このなかでも三角筋をのぞく3つの筋肉が、いわゆる「腕の筋肉」=「上腕筋群」と呼ばれています。 一般的に好んで鍛えられるのは上腕二頭筋(長頭・短頭)>上腕三頭筋(内側頭・外側頭)>上腕筋ではないでしょうか。そして、鍛えるのに技術がいる上、あまり目立たない(鏡で見えない非ミラーマッスル)である上腕三頭筋長頭の筋トレは軽視されがちです。 しかしながら、競技能力向上においては、上腕三頭筋長頭は非常に重要な筋肉部位であり、この部位の強弱が競技パフォーマンスに大きく影響します。また、腕を太くするという意味でも、上腕三頭筋長頭は上腕筋群のなかでもっとも体積が大きいので、最優先で鍛えるべき部位です。 ■上腕三頭筋長頭が競技に重要な理由●上腕筋群のなかで唯一体幹と接合しているからここで、上の画像をご確認ください。上腕三頭筋長頭は赤色で示された部位ですが、実は上腕筋のなかで唯一体幹部(肩甲骨)と接合している筋肉なのです。 他の上腕筋群の筋肉は、上腕最上部に位置する三角筋を通して体幹と連動しています。 上腕三頭筋長頭は、上腕三頭筋内側頭や外側頭が収縮限界をむかえた上腕と体幹のポジションから、さらに上腕を押し出す働きを持ちます。また、上腕部を内転=腕を上や横から閉じる作用もあり、特に上腕を肩関節より上に上げたポジションから下ろす動作に強く関係しています。 このことを、競技的に表現すると「最後の腕の押し込み」や「最後の腕の粘り」といった動作に強く関わっているため、この部位を鍛えることが競技能力向上に非常に重要とされているのです。 ■上腕三頭筋長頭の筋トレ方法●ディップス自重トレーニングで上腕三頭筋長頭を鍛えるのに最適な種目が、ディップスです。肘を体側につけ、やや斜め前に身体をおろしてからのすくい上げるような挙上動作のなかで、この部位に強い刺激を与えることができます。最後に数cm身体を押し上げる意識をすると、さらに効果的です。 なお、上腕三頭筋長頭に負荷を集中させるためには、できるだけ肘を閉じて(肘同士を近づけて)行うのがポイントです。 椅子を二つ使って自宅でも代用できますが、できれば家庭用のチンニング&ディップスタンドを用意して全身の自重トレーニングができる環境を揃えたいものです。 ●ベンチディップスまた、通常のディップを行うのが強度的に難しい方は、こちらの動画のようなベンチディップスが比較的強度が低くおすすめです。 ●ダンベルトライセプスプレスダンベル筋トレで上腕三頭筋長頭を直撃できる種目が、ダンベルを通常と反対に保持したダンベルトライセップスプレスです。ダンベルを押し上げたあとに、数cm絞り上げるように押し込むことで効果が高まります。あわせて、手の平をやや外に向ける方向に回旋させることで上腕三頭筋長頭が完全収縮し、効果が倍増します。 ●ダンベルキックバック上腕三頭筋の仕上げ単関節種目=アイソレーション種目としておすすめなのが、ダンベルキックバックです。肘を伸ばしたポジションで手の平を上に向ける方向に回旋させると、上腕三頭筋長頭が完全収縮し効果が倍増します。 ●オーバーヘッドダンベルフレンチプレスまた、オーバーヘッドダンベルフレンチプレスも、肩甲骨と直結している上腕三頭筋長頭を最大伸展させた状態からの収縮動作になるので、同部位に最適な種目の一つです。 ●バーベル筋トレバーベル筋トレで上腕三頭筋長頭を集中して追い込むことができるのがナローグリップベンチプレスです。一般的なナローグリップベンチプレスは、肩幅よりやや広いくらいのグリップ幅で行われますが、肘が外側に開くポジションでは上腕三頭筋長頭にはあまり負荷が加わりません。 肩幅よりやや狭いくらいのグリップ幅で、肘が体幹外縁の延長線上より外に出ないくらいの意識で行ってください。 ●バーベルフレンチプレスまた、ダンベルの場合と同様に、上腕三頭長頭を仕上げるのに最適な種目がオーバーヘッドフレンチプレスです。肘をできるだけ閉じて動作するのがポイントです。 なお、直線の通常バーベルですとグリップの角度的に手首間接へ負担がかかりますので、EZバーの使用をおすすめします。 ●マシンディップスマシンならディップスマシンがおすすめです。体重を乗せればかなり重い重量が扱えますが、体重を使わずに押しきれる重量でしっかり効かせるのが大切です。 ●トライセプスプレスダウンマシン筋トレで上腕三頭筋長頭を追い込むのに最適な種目がトライセップスロープを用いたケーブルプレスダウンです。 腕を下に押し込んだ状態から、やや腕を「ハの字」に開きながら、手首を回内(小指が外を向く方向)させることで、上腕三頭筋長頭が完全収縮します。 このトレーニングでは最終の腕を開く動作と回内動作がターゲットになります。その動作が確実に行えるよう、通常のプレスダウンのおよそ半分の重量設定がよいでしょう。 ロープアタッチメントは通常二種類の長さがありますが、上腕三頭筋長頭に効かせる場合は長いタイプを使用してください。 ●ケーブルキックバックケーブルキックバックは、上腕三頭筋のなかでも長頭に集中的な効果があります。 ケーブルキックバックは、肩関節を動かすと背筋群に負荷が逃げてしまいますので、肘を固定して肘から先だけで動作をすることが重要です。 また、肘を伸ばした位置で前腕を回内回旋(手の平が上を向く方向)させると、上腕三頭筋長頭が完全に収縮して非常に効果的です。 ●ケーブルフレンチプレスケーブルフレンチプレスは、上腕三頭筋に効果があり、フォームにより(肘の開き具合)、上腕三頭筋長頭から短頭(外側頭・内側頭)まで効果のある部位が変化しますが、肩甲骨に接合しており、肘を肩より上にあげた状態で最大伸展する長頭の性質を考え、オーバーヘッドでのケーブルフレンチプレスは長頭をターゲットにするのが定石です。...
【上腕三頭筋長頭の鍛え方】上腕筋群中で競技に最重要と言われる理由と筋トレ方法
上腕三頭筋長頭(一番体側の部位)は上腕筋群のなかでも、競技能力向上に最重要と言われています。その理由と、実際に筆者の運営しているジムで実践および指導している鍛え方のポイントを厳選してご紹介します...

【ぶり大根(ブリ大根)のカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
ぶり大根(ブリ大根)のカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。 ぶり大根(ブリ大根)とはどんな食べ物?ぶり大根(ぶりだいこん)は、ブリのアラを大根と一緒に醤油で煮付けた日本の郷土料理。ブリに脂が乗ってくる季節である冬の料理。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/ぶり大根 ぶり大根(ブリ大根)のカロリーと栄養素ぶり大根(ブリ大根)1食100gあたりのカロリー・栄養素は以下の通りです。エネルギー:83kcalタンパク質:5.12g (20.48kcal)脂質:3.85g (34.65kcal)炭水化物:5.36g (21.44kcal)ビタミン・ミネラルではビタミンB12が特に豊富です。なお、数値は「食品成分データベース(文部科学省)」を参照しています。 食事の三大栄養素について食事の三大栄養素(エネルギー産生栄養素)とは、タンパク質(protein)・糖質(carbohydrate)・脂質(fat)の三種類です。そして、その三種類の栄養素の頭文字をとって、栄養素バランスのことをPCFバランスと呼びます。 この三種類の栄養素の特徴とグラムあたりのカロリーは以下の通りです。 ○タンパク質(4kcal/g)タンパク質は筋肉を構成する物質で、筋トレで鍛えた筋肉を大きくするための材料となります。 ○糖質(4kcal/g)糖質は活動のためのエネルギー源になるだけでなく、タンパク質を筋肉として合成する時の筋肉合成カロリーとして働きます。 ○脂質(9kcal/g)脂質も糖質と同様のエネルギー源としての働きを持ちますが、グラムあたりの熱量が高く、貯蔵エネルギーとして効率的なので、余剰カロリーは体脂肪として貯えられます。 厚生労働省による三大栄養素に関する記載エネルギー産生栄養素(えねるぎーさんせいえいようそ) 食物中に含まれる身体に必須の成分のうち、たんぱく質・脂質・炭水化物の総称。 人間の身体になくてはならない栄養素のうち、エネルギー(カロリー)源となる「たんぱく質・脂質・炭水化物」を『エネルギー産生栄養素』と呼んでいます。以前は、三大栄養素とも言われていました。 引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-013.html 筋トレにおける各食品の食べ方高タンパク質低カロリー食品筋トレ後のタンパク質補給の食事の副食として最適です。ただし、食べ過ぎると脂肪になるので注意してください。 高タンパク質高カロリー食品バルクアップのためのタンパク質と筋肉合成カロリーの両方を含んでいるため、筋肥大トレーニング後の食事として効果的ですが食べ過ぎには注意してください。 低タンパク質高カロリー食品トレーニング前の運動エネルギー補給に適しています。トレーニング後に多く摂取すると脂肪になりやすいので注意が必要です。また、高タンパク質低カロリー食品に追加することで筋肉合成カロリーとして作用します。 低タンパク質低カロリー食品野菜やキノコ類などは食事の総量を物理的に増やすことができるため、ダイエット筋トレ時の食事のかさ増しに有効です。 トレーニングに有効なタンパク質食材筋力トレーニング後の食材として欠かせないのが高タンパク質・低カロリーな肉類・魚介類です。 そして、常にトレーニングに有効な食事を摂取するためには、日によって品質にばらつきのないよう、あらかじめ品質を確認した食材を冷凍ストックしておくといった工夫が有効的です。 ▼具体的なタンパク質食材例筋力トレーニングに有効な肉類・魚介類 食事・栄養に関する記事筋力トレーニングと食事・栄養に関する情報については、下記の記事をご参照ください。 筋力トレーニングと食事筋力トレーニングの栄養学筋力トレーニングと栄養補助食品筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
【ぶり大根(ブリ大根)のカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
ぶり大根(ブリ大根)のカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。 ぶり大根(ブリ大根)...

【ひつまぶしのカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
ひつまぶしのカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。 ひつまぶしとはどんな食べ物?蒲焼にしたウナギの身を切り分けた上で、お櫃などに入れたご飯に乗せ(まぶし)たものを、食べる側が茶碗などに取り分けて食べるのが基本的なスタイルであり、これが料理名の由来となっている。 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/ひつまぶし ひつまぶしのカロリーと栄養素ひつまぶし1人前500gあたりのカロリー・栄養素は以下の通りです。エネルギー:590kcalタンパク質:28.15g (112.6kcal)脂質:19.25g (173.25kcal)炭水化物:69.7g (278.8kcal)なお、数値は「食品成分データベース(文部科学省)」を参照しています。 食事の三大栄養素について食事の三大栄養素(エネルギー産生栄養素)とは、タンパク質(protein)・糖質(carbohydrate)・脂質(fat)の三種類です。そして、その三種類の栄養素の頭文字をとって、栄養素バランスのことをPCFバランスと呼びます。 この三種類の栄養素の特徴とグラムあたりのカロリーは以下の通りです。 ○タンパク質(4kcal/g)タンパク質は筋肉を構成する物質で、筋トレで鍛えた筋肉を大きくするための材料となります。 ○糖質(4kcal/g)糖質は活動のためのエネルギー源になるだけでなく、タンパク質を筋肉として合成する時の筋肉合成カロリーとして働きます。 ○脂質(9kcal/g)脂質も糖質と同様のエネルギー源としての働きを持ちますが、グラムあたりの熱量が高く、貯蔵エネルギーとして効率的なので、余剰カロリーは体脂肪として貯えられます。 厚生労働省による三大栄養素に関する記載エネルギー産生栄養素(えねるぎーさんせいえいようそ) 食物中に含まれる身体に必須の成分のうち、たんぱく質・脂質・炭水化物の総称。 人間の身体になくてはならない栄養素のうち、エネルギー(カロリー)源となる「たんぱく質・脂質・炭水化物」を『エネルギー産生栄養素』と呼んでいます。以前は、三大栄養素とも言われていました。 引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-013.html 筋トレにおける各食品の食べ方高タンパク質低カロリー食品筋トレ後のタンパク質補給の食事の副食として最適です。ただし、食べ過ぎると脂肪になるので注意してください。 高タンパク質高カロリー食品バルクアップのためのタンパク質と筋肉合成カロリーの両方を含んでいるため、筋肥大トレーニング後の食事として効果的ですが食べ過ぎには注意してください。 低タンパク質高カロリー食品トレーニング前の運動エネルギー補給に適しています。トレーニング後に多く摂取すると脂肪になりやすいので注意が必要です。また、高タンパク質低カロリー食品に追加することで筋肉合成カロリーとして作用します。 低タンパク質低カロリー食品野菜やキノコ類などは食事の総量を物理的に増やすことができるため、ダイエット筋トレ時の食事のかさ増しに有効です。 トレーニングに有効なタンパク質食材筋力トレーニング後の食材として欠かせないのが高タンパク質・低カロリーな肉類・魚介類です。 そして、常にトレーニングに有効な食事を摂取するためには、日によって品質にばらつきのないよう、あらかじめ品質を確認した食材を冷凍ストックしておくといった工夫が有効的です。 ▼具体的なタンパク質食材例筋力トレーニングに有効な肉類・魚介類 食事・栄養に関する記事筋力トレーニングと食事・栄養に関する情報については、下記の記事をご参照ください。 筋力トレーニングと食事筋力トレーニングの栄養学筋力トレーニングと栄養補助食品筋力トレーニング種目の一覧ページへ戻る筋肉の名称と部位ごとの筋トレメニューに戻る
【ひつまぶしのカロリーと栄養素】筋トレやダイエットでの筋肉との関係|タンパク質量
ひつまぶしのカロリーと栄養素(タンパク質・炭水化物・脂質)および筋力トレーニングとの関わり(摂取タイミング・筋肥大やダイエットでの食べ方など)について解説します。 ひつまぶしとはどんな食べ物?蒲...