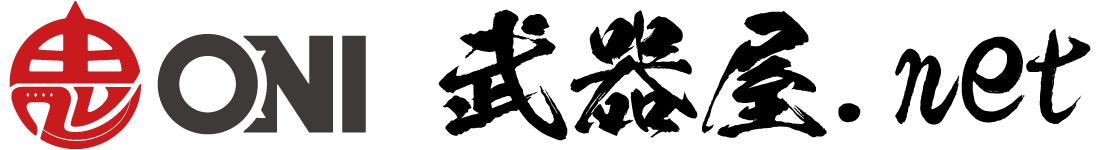片手腕立て伏せ(ワンハンドプッシュアップ)は、体育会系のクラブなどに所属した経験がある人は練習で行ったことも少なくない種目ですが、意外なほど高強度で、自重だけで大胸筋を筋肥大させるのには最適な種目の一つです。そのやり方とコツと注意点を解説します。あわせて、上手くできない人の練習に効果的な腕立て伏せもご紹介します。
■片手腕立て伏せが効果のある筋肉
●大胸筋・三角筋・上腕三頭筋
片手腕立て伏せ(ワンハンドプッシュアップ)は上半身の押す筋肉=大胸筋・三角筋・上腕三頭筋に効果があります。それぞれの筋肉の特徴と作用は以下の通りです。
●大胸筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:だいきょうきん
英語名称:pectoralis major muscle
部位詳細:上部|中部(内側)|下部
起始:鎖骨の内側|胸骨前面第2~第6肋軟骨|腹直筋鞘前葉
停止:上腕骨大結節稜
大胸筋は胸の筋肉で、上部・下部・内側に分けられます。上部は腕を斜め上方に押し出し、下部は腕を斜め下方に押し出し、内側は腕を前で閉じる作用があります。また、全てが共働して腕を前方へ押し出します。
●三角筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:さんかくきん
英語名称:deltoid muscle
部位詳細:前部|中部(側部)|後部
起始:鎖骨外側前縁|肩甲骨肩峰|肩甲骨肩甲棘
停止:上腕骨三角筋粗面
肩の筋肉である三角筋は前部・側部・後部に分けられます。前部は腕を前へ、側部は腕を横へ、後部は腕を後ろに上げる作用があり、全てが共働して腕を上へ押す上げます。
●上腕三頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:じょうわんさんとうきん
英語名称:triceps
部位詳細:長頭|外側頭|内側頭
起始:肩甲骨関節下結節|上腕骨後面|上腕骨後面
停止:尺骨肘頭
腕の後側の筋肉である上腕三頭筋は長頭と短頭(内側頭・外側頭)に分けられ、長頭は肘関節の伸展と肩関節の内転、短頭は肘関節の伸展をさせる作用があります。
■片手腕立て伏せができる条件
●ベンチプレス自重挙上+バランス技術
片手腕立て伏せを行うのには、やはりそれなりの筋力が必要となります。目安としては、ベンチプレスで自重を挙上する程度の筋力となりますが、筋力以外にもバランスをとる技術が必要となります。
■片手腕立て伏せのやり方
●足を大きく開き重心に手を置く
片手腕立て伏せが上手くできるかどうかは、筋力以外にバランスが上手くとれるか否かということがポイントになります。バランスをとりやすくするために、大きく足を開くとともに、手は全身の重心となるみぞおち付近の直下に置きます。
また、上体を手をついた方へ軽く斜めに傾けることで、さらにバランスがとりやすくなります。
【本種目のやり方とフォームのポイント】
①足を大きく開き、背すじを真っ直ぐにし、身体の中央に手を置いて構える
②肩甲骨を寄せたまま、背すじも真っ直ぐに保って身体を下ろす
③身体を下ろしたら、反動を使わずに肘を伸ばして身体を押し上げる
④身体を押し上げたら、やや顎を引いてしっかりと大胸筋を収縮させる
※動作中は、お腹を突き出したり、腰を曲げたりしないように注意してください。
■片手腕立て伏せが上手くできない場合
●ボールを使って練習すると効果的
片手腕立て伏せを行うためには、ベンチプレスで自重を挙上する程度の筋力が必要になりますが、その筋力があるにもかかわらず片手腕立て伏せができないという方は、動作自体に慣れていく必要があります。
そのために最適な練習方法が、こちらの動画のようなバールを使った半片手腕立て伏せや、下記のようなアーチャープッシュアップが効果的です。
こちらが、アーチャープッシュアップの模範的な動画です。どうぞご参照ください。
■片手腕立て伏せの注意点
●無理をせず肘関節は90度屈曲まで

片手腕立て伏せは、高強度の自重トレーニングですので、筋力的に余裕のない状態で行うと肩関節や肘関節に大きな負担がかかります。特に、肘関節を90度以上曲げた状態では肘関節に大きな負荷がかかります。確実に動作を行なう自信のない方は、肘を90度以上曲げないように注意してください。
■片手腕立て伏せの目的別の重量負荷設定

筋トレで鍛える骨格筋を構成している筋繊維には以下の三種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。
①速筋繊維TYPE2b
約10秒前後の短い時間に爆発的・瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより強く筋肥大します。10回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。
②速筋繊維TYPE2a
10~60秒ほどのやや長時間で瞬発的な収縮をする特徴があり、トレーニングによりやや筋肥大します。15回前後の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。
③遅筋繊維TYPE1
60秒以上数分・数時間の持続的・持久的な収縮をする特徴があり、トレーニングにより筋肥大せずに筋密度が上がります。20回以上の反復回数で限界がくる重量設定で鍛えます。
つまり、筋肥大バルクアップ目的なら①、細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップ目的なら②、減量引き締めダイエット目的なら③、の負荷回数設定で筋トレを行っていきます。ただし、腹筋郡・前腕筋郡・下腿三頭筋など日常での使用頻度が高い部位は、基本的に20回以上高反復回数で鍛えます。
■腕立て伏せにはプッシュアップバーを

腕立て伏せ系のトレーニングをするのに、ぜひとも用意したいのがプッシュアップバーです。手首を真っ直ぐに保てるので関節を保護できるだけでなく、動作の可動域自体が広がるため、トレーニングの効果が倍増します。
▼関連記事
【おすすめプッシュアップバー】胸筋トレーニングの効果を高める器具の種類や使い方
■おすすめの記事
【自重トレーニングメニュー】限界突破の最強筋肥大筋トレを解説
■自重トレーニングの基礎知識

●自重トレーニングの長所と短所
自重トレーニングは器具が必要ないため、いつでもどこでも手軽に取り組めるのがメリットです。
一方、自重トレーニングには複数の筋肉・関節を同時に動かす複合関節運動(コンパウンド種目)しかなく、個別の筋肉を単関節運動(アイソレーション種目)で集中的に鍛えるのが難しいというデメリットがあります。
ですので、自重トレーニングの後に仕上げとしてチューブトレーニングやダンベルトレーニングを行うのが理想と言えます。
●自重トレーニングの負荷の上げ方
自重トレーニングの負荷の上げ方には、主に以下の方法があります。
①動作をゆっくり行う
②重りを身体につける
③一番負荷のかかる位置(スティッキングポイント)で動作を一度静止する
なお、他の自重トレーニングメニューについては、下記の種目別解説記事をご参照ください。