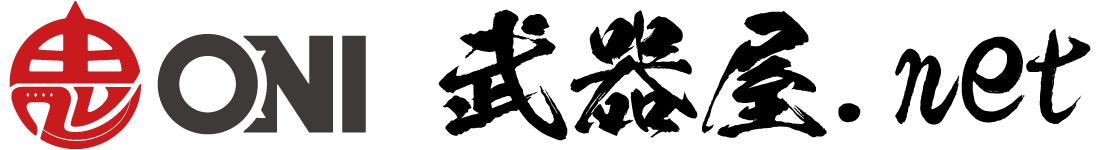視力の良い悪いとは何か、その種類をふくめて解説するとともに、一般的に定番とされている視力回復方法を解説します。あわせて、スポーツ競技の能力向上にも有効な「動体視力」を向上させる最先端のメガネもご紹介します。
■視力が悪いとは?
●主に近視と遠視と乱視がある

ものを見る場合、眼球表面の角膜を通過した光はレンズの働きをする水晶体によって集められた後、網膜中心の黄斑に結像します。
結像した光は視神経により脳に情報が伝達され、それを視覚として認識しています。
一般的に視力が悪いと呼ばれる状態には「近視」「遠視」「乱視」の三種類があり、それぞれの特徴と原因は以下の通りです。
●近視
角膜のカーブが強い、または眼軸が長い(角膜から網膜までの距離が長い)ことが原因となり、網膜よりも手前に像が結像してしまう状態です。もっとも多い症状で、思春期に始まり20代頃まで進行した後に状態が落ち着く場合がほとんどです。遠くのものがぼやけてしまいます。
●遠視
角膜のカーブが弱い、または眼軸が短い(角膜から網膜までの距離が短い)ことが原因となり、網膜よりも奥に像が結像してしまう状態です。多くの場合は加齢にともない進行し、いわゆる老眼と呼ばれる状態もこれにあたります。近くのものがぼやけてしまいます。
●乱視
角膜の表面に凹凸があるなどが原因となり、一点に像が結像しない状態です。先天的な要素が強く専用のメガネ類で補正します。
■視力回復の対象は主に近視

視力回復の対象とされるのは主に近視ですが、近視には眼軸の長さに起因する「軸性近視」と水晶体の屈折率が強すぎる「屈折性近視」に分けられます。
このなかで、視力回復の対象となるのは屈折性近視で、その大きな原因一つとして考えられているのは、読書やポータブルゲーム・スマホの長時間連用によって、眼球が緊張し、水晶体が厚くなって屈折率が上がり(ピントの固定化)、そのまま真性近視に移行するというパターンです。
このほかにも、遺伝的要因、栄養状態なども大きく影響するとされています。
そして、視力の回復のために、眼球の緊張をやわらげ、角膜が膨らんでしまう状態を避ける、または緩和するさまざまな方法が考案されていますので、代表的な方法をご紹介していきます。
■目を温める
長時間の目の使用で「目が疲れた」と感じたときに良いとされているのが、蒸しタオルなどで目を温めることです。目を温めることで、周辺の血行がよくなり、緊張もほぐれ、視力回復の効果も期待できると言われる定番の方法です。
■目を冷やす
長時間の目の使用で「目が充血した」ときに良いとされるのが、冷やしタオルなどで目を冷やすことです。これにより充血が緩和され、視力回復にも効果が期待できるとされている人気の方法です。
■マッサージをする
こちらは、目の疲れをとる「眼精疲労簡単ケアマッサージ」です。目を疲労させないことが、視力回復への第一歩と一般的には言われてますので、このようなマッサージも効果が期待できるのではないでしょうか。
■目の体操をする
●指を見ることで目を動かす
こちらの動画は指を動かしながら、指の動きを目で追うことで行う「目の体操」です。左右、上下、円運動とさまざまなアプローチによってまんべんなく目を体操させることが可能です。
●動画を見て目を動かす
こちらの動画は「グリーンボール」と呼ばれる有名な目の体操動画です。首を動かさずに、目の動きだけで緑の玉の動きを追うことで、目の体操ができます。
左右方向→上下方向→二倍速上下方向→四倍速左右方向と運動をした後、最初の速度でクールダウンを行うという内容です。
●静止画を見て目を動かす

こちらの画像は3Dステレオグラムと呼ばれる特殊な画像で、目の焦点をずらし、ボーっと画像を見ていると3D画像が浮き上がるというもので、3Dステレオグラムと呼ばれています。
ステレオグラムを見る動作のなかで、目の緊張が緩和されると言われており、視力回復にも効果が期待できるとされる人気の方法です。
なお、この画像をうまく立体視できるとハートマークが浮かび上がってきますので、ぜひチャレンジしてみてください。

また、こちらのステレオグラムは、上手く見ることができると「3D」という文字が浮かび上がってきますので、あわせてチャレンジしてください。
■専用のメガネを使う
●ピンホールメガネ
画像引用:Amazon
こちらは、ピンホールメガネを呼ばれる視力回復が期待できるとされているメガネです。

目を細めるとピントが合いやすくなりますが、これは目の「f値」を高くすることで「被写界深度」=「ピントの合う範囲」を広げられることが原因です。
「f値」とは「レンズ直径」を「焦点距離」で割った値で、「f値」の数値が高いほどピントの合う範囲「被写界深度」は深くなります。
目の場合は焦点距離は変えられませんので、目を細めてレンズ直径を小さくし、それにより「f値」を上げ被写界深度を高めることが可能です。
この原理を利用したのがピンホールメガネで、小さな穴を通してものを見ることでピントが合いやすくなり、結果として視力回復にも効果があるのではと考えられています。